「世界の幸せをカタチにする」
学生たちの挑戦
2019.3.1 <世界の幸せをカタチにする。><学生たちの挑戦>
ダイバーシティ
×
武蔵野大学
×
武蔵野大学
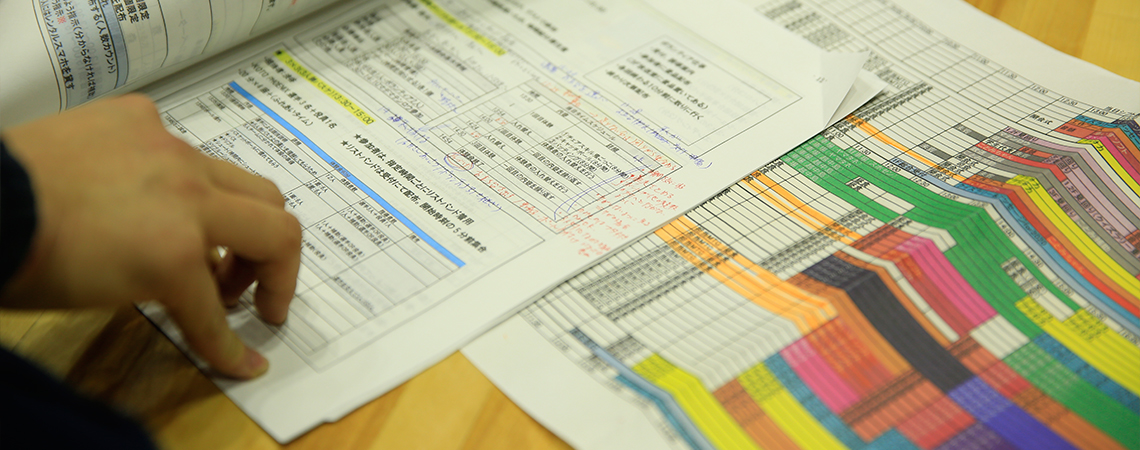
学生でもできること、
学生だからできること。をしよう、
スポーツマネジメントゼミ。
本学では、学生のキャリア開発を目的に、所属学部での学びに加え副専攻の学びとして、学部横断型のゼミナール「サブ・メジャーゼミ」を開講しています。教員に実務家をむかえ、第一線で活躍するプロから、知識やスキルを学んでいきます。分野は、スポーツマネジメント、地方行政・図書館司書、コピーライティング、国際関係など多岐にわたります。2・3年次の2年間で、演習形式の授業に加え、長期学外学修に取り組み、1年次に身につけた「知の土台」を自身のキャリアへと繋げていきます。
2014年にスタートしたスポーツマネジメントゼミでは、スポーツ系企業のコンサルティングやPR・広報活動を手がける上村智士郎先生を教員にむかえ、ビジネススキルや知識を学んでいます。まず、2年次の前半にマネジメントの基礎や五輪大会への理解を深めます。その後、障がい者スポーツ体験会の自主開催や他の団体が運営する障がい者スポーツイベントに参加して、マネジメントやマーケティング、組織づくり、広報活動について、実践を通して学んでいきます。その他にも、車椅子ソフトボールの国際大会の運営や大会後の表彰式、懇親会の企画運営を通して、ファシリテーションのスキルも身につけています。過去に開催した障がい者スポーツチャレンジをきっかけに、車いすソフトボールの競技団体の活動をゼミ生がサポートするなど、交流の継続性を図ることにも努めています。ゼミ生たちは修了後も、学んだスキルを自身の学部の学びに活かしながら、実社会におけるダイバーシティ実現に貢献していきます。
2014年にスタートしたスポーツマネジメントゼミでは、スポーツ系企業のコンサルティングやPR・広報活動を手がける上村智士郎先生を教員にむかえ、ビジネススキルや知識を学んでいます。まず、2年次の前半にマネジメントの基礎や五輪大会への理解を深めます。その後、障がい者スポーツ体験会の自主開催や他の団体が運営する障がい者スポーツイベントに参加して、マネジメントやマーケティング、組織づくり、広報活動について、実践を通して学んでいきます。その他にも、車椅子ソフトボールの国際大会の運営や大会後の表彰式、懇親会の企画運営を通して、ファシリテーションのスキルも身につけています。過去に開催した障がい者スポーツチャレンジをきっかけに、車いすソフトボールの競技団体の活動をゼミ生がサポートするなど、交流の継続性を図ることにも努めています。ゼミ生たちは修了後も、学んだスキルを自身の学部の学びに活かしながら、実社会におけるダイバーシティ実現に貢献していきます。
4回目の開催をむかえた
障がい者スポーツ体験イベント「障がい者スポーツチャレンジ」

2018年12月9日に、東京都江東区にある深川スポーツセンターで、スポーツマネジメントゼミが企画運営する「障がい者スポーツチャレンジ2018」が開催されました。一期生が江東区に提案したアイデアをもとに、2015年から毎年開催されているゼミの伝統イベントです。開催に向けて、企画から外部交渉、当日の全体進行まで学生達が主体となって進めてきました。開会式では、本学のスポーツマネジメントゼミ代表として佐合さんが主催者挨拶を果たし、江東区の障がい者和太鼓サークル「エンジョイクラブ」と、武蔵野大学和太鼓サークル「隼」の共演も行われました。こうした活動を通じて、ダイバーシティ社会実現に向けたメッセージを発信することができました。イベントでは、車椅子ソフトボールチームの東京レジェンドフェローズの方々による車椅子ソフトボール体験会や、アイマスクをして音や周りの指示を頼りにボールを蹴るブラインドサッカーや、車いすバスケットボールチーム「LaVitz」と、2020年東京五輪新種目でもある、3人制バスケットボールチーム「江東フェニックス」とのシュート対決等で、イベント会場全体で大変な盛り上がりを見せていました。その他にも、オリンピック・パラリンピックへの理解を深めるクイズラリーやVR工作、東京五輪音頭など、子どもから高齢者の方まで楽しめる1日をプロデュース。地域のみなさまに障がい者スポーツを通してダイバーシティ社会への理解向上と、江東区の活性化を目指しました。
一緒に考えながら
これからのダイバーシティを盛り上げていきたい。
車椅子ソフトボールは、アメリカで誕生したスポーツです。現地では、メジャーリーグ同様にワールドシリーズが開催されるなど、メジャーな存在です。日本でプレーされるようになったのは、おおよそ7年前。まだまだ存在自体を知らない方が多くいます。今回のイベントでは、子どもたちに実際に車椅子でプレーしてもらえたことが、とても良かったと思います。プレーヤーの年齢層も広く、参加しやすい車椅子ソフトボールは、スポーツを通して障がい者と健常者の接点を探す、格好のフィールドになると思っています。パラリンピック東京大会が終わった後も一緒に活動し、少しでも隔たりをなくしていけたらと思っています。
関東車椅子ソフトボール協会
東京レジェンドフェローズ
池内陽彦さん
関東車椅子ソフトボール協会
東京レジェンドフェローズ
池内陽彦さん

子ども達がダイバーシティを五感で感じて、
視野を広げるイベントを。

今回、私たちが企画運営したイベントは、スポーツを通して参加してくださった皆さんに、頭でっかちにならず五感でダイバーシティを感じとり、視野を広げるきっかけになることを目指しました。上村先生がゼミ生同士の話し合いや、考える時間をしっかりと設けてくださったので、仲良しメンバーといった感じではなく、一人ひとりが責任感を持ってイベントに取り組めたと思います。決して大きなイベントではありませんでしたが、地域や行政の多くの方々にご協力いただき、学ぶことがたくさんありました。イベントに関わる全員が同じ熱量になることは簡単ではありませんが、熱を上げていくこともマネジメントの大切な役割だと、身をもって学びました。このゼミでの学びを、経営学部での学びにも活かしていこうと思います。
経営学部 経営学科 3年
佐合 緑さん
経営学部 経営学科 3年
佐合 緑さん
インプットと同じ量、もしくはそれ以上のアウトプットを。
実践する大切さを学びました。
武蔵野大学に入学したときから、東京オリンピック・パラリンピック大会に携わりたいという想いがあり、スポーツマネジメントゼミに入りました。このゼミで一番学んだことは、アウトプットの大切さです。自分で実践して、振り返って、もう一度トライする。その繰り返しを続けていくことで、知識は定着すると2年間で身をもって学びました。このゼミは3年で終わってしまいますが、東京オリンピック・パラリンピック大会への理解を深めていくなかで、大会を絡めた企業のブランディング戦略や開催国と参加国の文化交流など、これから学びたいことも発見できました。4年次では、就職活動と並行しながら、その領域をしっかり勉強しようと思っています。
グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 3年
初鹿 雅也さん
グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 3年
初鹿 雅也さん

オリンピック・パラリンピックが終わっても心に残るものを。

このゼミでは、学びを実践することに加えて、人の繋がりを広げていくことにも積極的に取組みました。その一つに、自主企画したトークセッションでは、「レガシー」という考え方を教わりました。単語の通り、遺産や伝承するという考えです。オリンピック・パラリンピックを一過性のイベントと捉えるのでなく、終わった後も地域や心に残る体験や思い出をつくっていこうというものです。この考えに、私はすごく共感し、東京オリンピック・パラリンピック大会を通してダイバーシティへの理解を深める人口を増やさなくていけないと思っています。まずは自分ができることから挑戦しようと考えていて、東京オリンピック・パラリンピック大会をきっかけにたくさんの方にお会いして、日本の文化を広めていきたいです。そのために、日本をもっと知るだけでなく、表現力や語学力等のコミュニケーション能力を磨いていこうと思っています。
グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 3年
渋谷 香菜さん
グローバル学部 グローバルコミュニケーション学科 3年
渋谷 香菜さん
担当教員の声
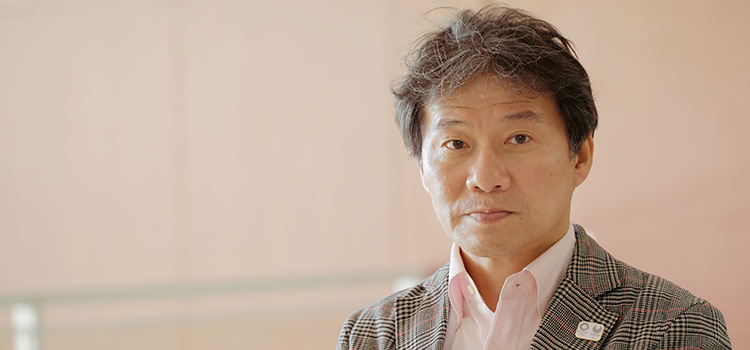
スポーツマネジメントゼミ
上村 智士郎客員講師
このゼミでは、学外でのイベント開催など自主的、自発的をモットーとする活動を実践する中で、マネジメントスキルを学修することを目的として、計画・行動・評価・改善のPDCAをしっかりと深めて、実行できる力を2年間で養っていきます。毎年、先輩達のイベントでの成果を引き継ぎながらも、更に後輩達がPDCAを回し、そして磨き上げてくれている良い流れが、スポーツマネジメントゼミにはあります。それを絶やさないように見守るのが私の役目だと思っています。「学生でもできる、学生だからできる」。学生が持っている力を引き出し、これからも成果を社会に還元していきます。

関連リンク
武蔵野大学スポーツマネジメントゼミ
https://www.spomane-semi.com/
スポーツマネジメントゼミ主催『障がい者スポーツチャレンジ2018』
https://www.musashino-u.ac.jp/event/20181209-00000271.html
https://www.spomane-semi.com/
スポーツマネジメントゼミ主催『障がい者スポーツチャレンジ2018』
https://www.musashino-u.ac.jp/event/20181209-00000271.html

