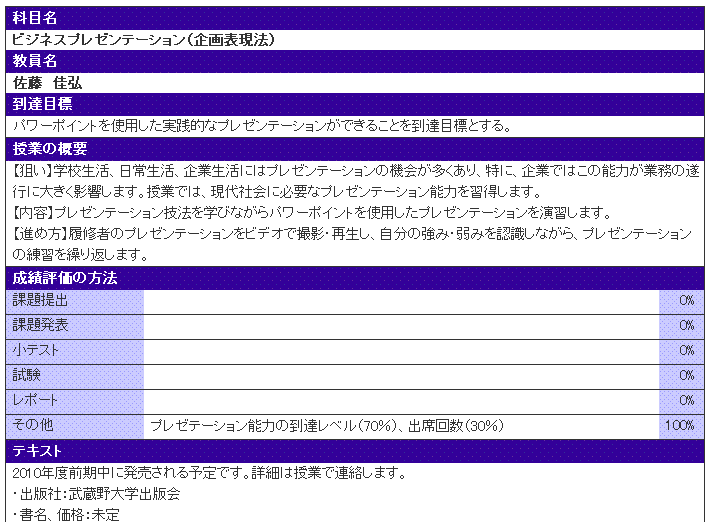
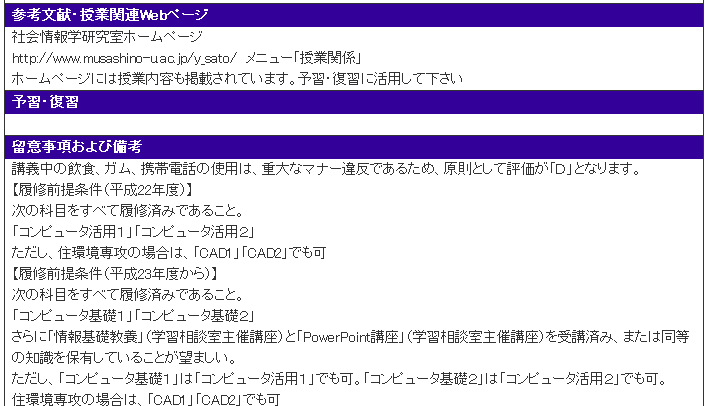
シラバスに訂正があります。
【履修前提条件(平成22年度)】
(誤)「コンピュータ活用1」「コンピュータ活用2」
↓
(正)「コンピュータ活用1A」「コンピュータ活用1B」
| 第1回 ガイダンス |
前期と後期とでは、内容は同じです。自分の都合のよい方で履修して下さい。
1.成績評価の基準
【S】出席良好であり、かつ、優れたプレゼンテーションができる。人数は履修者の5%が目安である。
【A】欠席回数が1/3未満であり、プレゼンテーションは一定の水準に達している。
【B】欠席回数が1/3未満であり、プレゼンテーションにはもう一歩の努力が必要である。
【C】欠席回数が1/3以上であるが、プレゼンテーションは一定の水準に達している。
【D】(1)欠席回数が1/3未満だが、プレゼンの確認を受けていない。
(2)授業中にガム、飲食、携帯電話、音楽プレーヤーの操作があった。
【X】欠席回数が1/3以上、かつ、プレゼンの確認を受けていない。
履修者の声(シャトルカードより)
<2009年度前期>
「今まで授業を受けてきて、プレゼンをすることに対しての恐れが全くなくなりました。
見違えるほど変わった気がします。」(英語・英米文学3年)
「この授業は私の期待をはるかに超えるもので、履修して良かったと思います。」(英語・英米文学3年)
「前期の授業で1番楽しい授業でした。」(社会福祉3年)
「とても有意義な授業でした。」(環境3年)
2.授業内容:半年間でこんなことをやります
3.試験:実施しません
この授業はPowerPointを教える授業ではありません。プレゼンテーションを教える授業です。
効果的なプレゼンテーションの方法を学びます。 「ビジネスプレゼンテーション」がパソコンの授業だと思ったら大間違い! PowerPointを使用しますが、パソコンは道具としてしか使いません。
2回のプレゼン演習があり、ビデオ撮影・再生を行います。
科目名に付いている副題(企画表現法)は、古い名称のまま残っているものです。
この科目は「企画」ではなく、プレゼンテーションを教える科目です。
プレゼンテーションのスキルを見ます。4.テキスト
5.定員40名
『できる!伝わる!プレゼン力』佐藤佳弘著、武蔵野大学出版会、1,785円(税込み)
もしも、履修者が定員を超えていたら、抽選で履修者を決定します。6.その他の項目 ←クリックして下さい。
(1)卒業年度の学生(4年生)は、卒業に関わるため抽選をせずに履修を認めます。<第1週目の授業が定員以内で、第2週目で定員を超えた場合>
(2)欠席者は抽選に参加できません。代理抽選も不可です。
(3)半年前や1年前に落選経験がある人の優遇はありません。平等に抽選します。
第1週目に出席した人の履修を優先にして、抽選を行います。
当選者はガイダンスを続けるので残って下さい。
第2回 プレゼンテーションの基本(良いプレゼン、悪いプレゼン)
(1)プレゼンテーションって?
イスを持って教卓前に集まりましょう。先生が説明します。(2)グループディスカッション
<内容>(3)ディスカッション結果の整理
みんなにとって最も身近なプレゼンテーションである学校の講義を例に考えてみよう。 これまで受けた大学の講義を思い出して下さい。その中には、良かった講義や 悪かった講義があるでしょう。それぞれの講義について、どんな点が良かったのか、 どんな点が悪かったのかをグループでディスカッションします。
「良い講義」を「良いプレゼン」と置き換えて、聞き手から見た 「良いプレゼン」の条件を箇条書きにして整理します。(4)レポートの作成
次に、それらを内容別に大きく分類し、それぞれの分類に「〜について」という分類名を 小見出しとして付けます。
(例)「配布資料について」「声について」など
整理した結果をグループでレポートにします。(5)最重点項目の決定
「良い講義」を「良いプレゼン」と置き換えて、良いプレゼンの要素を レポートにまとめます。すべて箇条書きにします。
「良いプレゼン」の項目から、これだけは譲れないという 最重点項目を3点選びます。その3点に文字飾りをして強調しましょう。(6)レポートのチェック
レポートができたら印刷して先生のところへ持って行きましょう。 先生が過去のレポートを見せてくれるので、参考にします。 さらに項目を追加してレポートを完成させます。
先生からOKが出たら、グループ全員の分も印刷して、各自で持ちましょう。 今後の大切な資料になります。
第3回 60秒プレゼンの演習
今週は、さっそく 何も使わないプレゼンテーション に取りかかります。
(1)プレゼンの準備
短いプレゼンテーションを練習します。(2)60秒プレゼン
これからみんなが目指すのは、「良いプレゼン」です。 題材は自己紹介です。シーンは、新しいバイト先、ゼミ、サークル、コンパ、 就職先など、自由に設定してよいです。どんなシーンにしてもよいです。
・スタートの合図はしません。立ち位置に立ったら、自分でスタートします。
・60秒を経過しても合図はしません。
・場の設定は説明する必要はありません。
・自己紹介が終わったら、拍手をしましょう。
このプレゼン演習は、録画・再生して相互評価をします。 授業は始まったばかりなので、今はプレゼンが下手で当然です。 自分のプレゼンを映像で見るのはとてもつらいことですが、レベルアップのためです。 がんばりましょう。もちろん、先生はこの録画を授業以外で使用することは ありません。安心して下さいね(^_^)
第4回 プレゼンの研究
いくつかのプレゼンのサンプル映像を見て、人を引き付けるプレゼンの要素を考えます。
(1)グループ編成
6人前後のグループを作ります。
(2)6・6法でのディスカッション
テーマ「プレゼンで初心者が困ること」
・フリーディスカッション
・書き出しながらディスカッション
第5回 60秒プレゼンの評価
(1)60秒プレゼンのレビュー
前回の録画を再生して、プレゼンについて相互評価します。
ほとんどの人の一番の失敗は、あれもこれもと詰め込み過ぎていることです。 内容が総花的であるために、結局は聞き手に何の印象も残りません。 自分たちが作った「良いプレゼン」の項目をもう一度よ〜く読みましょう。 聞いていて何を言いたいのかポイントがわからない、というのは悪い例です。
あなたは何を伝えようとしたのですか?それは、相手が望んでいたものですか?
第6回 PowerPointによる電子スライドの作成(スライドのデザイン)
(1)これまでのレビュー
・良いプレゼン(2)プレゼンの悩み、困ること
・60秒プレゼンの演習
・自分のプレゼンの再生
・先生の自己紹介サンプル
(3)パワポプレゼン課題の説明
第7回 PowerPointによる電子スライドの作成(第一印象、緊張への対策、適切なスライド数)
(1)テキスト「スライド作りのポイント」
(2)緊張しやすい人のために
(3)適切なスライド数
第8回 PowerPointによる電子スライドの作成(目線の重要性、いけないプレゼン)
(1)テキスト「プレゼンタブー集」
(2)電子スライドを使ったプレゼン事例
・スライドを使ったプレゼンの実例(CDMの紹介)(3)パワポの効果
・スライドの切り替え効果
・アニメーション効果
・背景画像の入れ方
第9回 PowerPointによる電子スライドの作成(話し手の悩み、聞き手のプレゼン)
(1)話し手の悩み
・緊張する。
・どこを見たらいいのかわからない。
・手が動いていいのだろうか?
・姿勢が丸くなってしまう
・考えていたのに言うことを忘れる
・何分話したのかわからない
(2)ありがちな失敗プレゼン
(3)聞き手のプレゼン
・パソコンを使いながら
・他の方向を向いたまま
・携帯電話の操作
・腕組み、足組み
第10回 PowerPointによるプレゼンテーションの演習
プロジェクターに表示しながらプレゼンテーションを行います。
このプレゼンテーションは、これまでの授業の総合評価になります。
<ポイント>
(1)話し方
(2)内容・構成
(3)スライドの作り方
の3点について
・講義内容が身に付いているか
・ホームページに記載されている事項を守っているか
・これまでに受けた受けた指摘を改善したか
を重点に評価します。
プレゼン時間は授業で指定します。
第11回 PowerPointによるプレゼンテーションの評価(1)
ビデオを再生してプレゼンを相互評価します。
他の人のプレゼンに対して、良い点・悪い点を指摘できるかどうかも 評価の対象です。なぜかというと、授業を理解していなければ指摘が できないからです。「よかったです」だけのコメントは、どの点が どのようによかったのかが不明なため、×です。良い点・悪い点を 具体的に指摘して下さい。
<自己評価のポイント>
(1)内容について
相手に伝えるべきことが絞られているか?
特に
・プレゼンの所要時間を大幅に超えた人→リベンジ
明らかに練習不足、準備不足です。
(2)話し方について
相手に伝わる話し方をしているか?
特に
・語尾が「〜てぇ、〜しぃ、〜でぇ」の人→リベンジ
・下ばかり見て話している人→リベンジ
(3)PowerPointのスライドについて
相手に伝わるように作ってあるか?
特に
・項目だけで、その内容にポイント、結論、言いたいことが書かれていない人→リベンジ
「だから何なのか」「何が言いたいのか」がスライドでわかるように!
次の人は次の週にプレゼンをもう一度やります。
(1)プレゼンの所要時間が大幅に超えた人
(2)内容・構成を改善するように指示された人
(3)話し方を改善するように指示された人
(4)再チャレンジを希望する人
(5)PowerPointによるプレゼンを欠席した人
次の人は次の週にスライドを提出し直します。
(1)スライドを改善するように指示された人
(2)再提出を希望する人
第12回 PowerPointによるプレゼンテーションの評価(2)
前週に引き続きプレゼンを相互評価します。
第13回 リベンジプレゼン
プレゼンテーションの再チャレンジをします。
第14回 リベンジプレゼンの評価
リベンジプレゼンを相互評価します。第15回 まとめ
まとめ第16回 補講(予備)
補講(予備)予備