受講生の声 - 宇津 帆香 さん

宇津 帆香 さん
工学部 環境システム学科 2年(2023年度)
2年前期 プログラミング発展B
”主専攻の学びを拡張させるための手段を学ぶことができる”
授業を受ける前の印象
プログラミングに興味はあったものの、言語などの知識は全くありませんでした。1年で受講していた「プログラミング基礎」の課題に苦戦した思い出があるため、不安がありました。しかし、この授業を受講した先輩方も同じように言語の知識が無い中で始めて、最終的に一つの作品を完成させられるまでになったというお話を聞きました。きっとほとんど知識が無い人でも授業内でプログラミングについての基礎知識や、課題解決方法を学ぶことができるのだろうと思いました。
授業を受けるにあたって特に準備したことはありませんが、私はこの授業のように個人作業をする場合、集中しすぎて気づいたら時間が経っていることがよくあります。そのため、この授業の前後に別の授業を入れないようにして、作業だけに熱中できるような環境づくりをしていました。
授業を受けるきっかけや動機
プログラミング教育はすでに小学校でも必修化されています。つまり、私たちが社会に出てからプログラミングスキルは「学んでいて当然のもの」となってくるのだと思います。私は年を重ねても時代に置いて行かれないような大人になりたいと思っています。そのためには常に新たな世代が持っているスキルや価値観を積極的に学ぶ必要があると考えたため、この授業の受講を決めました。武蔵野大学では、全学科の学生がプログラミングの授業を受講でき、私がこの大学を志望した理由の一つでもありました。
授業で体験したこと
授業はオンデマンドで各自学習を進める時間と、オンライン同時双方向で行う作業の時間で構成されていました。オンデマンド授業は、講義資料とpaizaラーニングというプログラミングの講座サイトを利用しました。paizaラーニングでは、解説動画を見ながら実際にコードを書く練習ができます。かなり初歩的なところから解説されているため、自分が苦手とする部分を埋めながら進められて勉強になりました。今回の授業ではHTMLとJavaScriptの講座を学びましたが、ほかのプログラミング言語の講座も多くあったため、こっちも学んでみたい!と思いながら受けていたのを覚えています。
同時双方向の時間は、少人数の班に分かれて課題に取り組みます。「このような動きをするプログラムを作ってください」という課題が出され、「どのような処理を行えば課題通りの動きをするか?」を考えながらコードを書いていきます。処理方法が思いつかなかったり、コードを書いても想定通りに動かず困ったりした場合は、担当の先生に質問をすれば理解できるまで教えてくれます。オンライン上で質問するのに最初は不安がありましたが、作業している画面を共有することで、私がコードを書く様子を実際に先生が見ながら親身になって教えていただきました。
最終課題は、それまでの授業で得た知識を基に自分の理想をどこまで実現可能かを測ることを目的として、個人でプログラムを作成するミニプロジェクトでした。どのようなアプリケーションが作りたいかという企画書を提出し、それに沿って制作していきました。
私は、絶滅危惧種の動物についてユーザーに学んでもらうクイズゲームのWebアプリを制作しました。

絶滅危惧種を探せ!第1問画面

絶滅危惧種を探せ!ゲーム終了画面
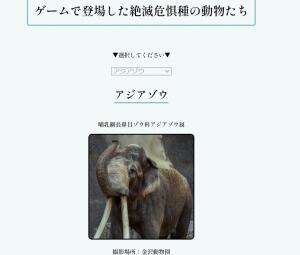
ゲームで登場した絶滅危惧種の動物たち選択画面
授業を受けて印象に残ったこと
最後の授業で自分が制作したアプリケーションを発表し、学生と先生方にレビューをしてもらいます。私は課題の中で特にデザイン性に力を入れており、フォントや色合いなどは気に入ったものを使って作っていました。しかし、この相互レビューの時間で「このフォントだとユーザーからすると読みづらい」という意見が出ました。確かに、実際の現場でプログラムを作るときは自己満足だけでなく、「第三者からどう見えるか?」が大切になります。私は最終課題をあくまで「課題」として制作していたため、自分が好きなように作りすぎたのだと気づきました。更には私の作品をよりよくするために、「クリックしたときに動物の鳴き声の音を付けてみたらどうか?」などの案ももらうことができました。個人作業だけで完結していたらきっと得ることができなかった視点を得ることができました。多くの人に受け入れられるものをつくるには、個人作業で完結させず、できるだけ多くの人に意見をもらいながら作る必要があるということに気づきました。自分の作品に、先生方のようなプロの視点での意見がもらえるこの相互レビューの時間は、非常に有意義だったと感じています。
授業で努力したこと「自分が一番楽しめるものを作る」
最も努力したのは、作っている間も作った後も自分が一番楽しめるものを作ることです。自分の理想をできるだけ実現させるためには、複雑な処理が必要でした。具体的には、ゲームクリア後の別ページへの遷移です。企画書を書いた時点では、ゲーム内に登場した動物についての外部サイトのURLを載せる予定でした。しかし既存のホームページのURLというのはHTML内での扱いがかなり難しかったため、外部サイトではなく自分で書いた別ページへ遷移させるという処理を行いました。これは授業内で学んでいない処理方法でしたが、どうしても実装したかったため挑戦しました。授業で学んでいない部分であったとしても、同時双方向授業の中で先生方がサポートしてくださるため、安心して取り組むことができました。ただ、相互レビューでは、ゲームのインターフェースとして複雑なため、この処理はあまり良いものではないという意見をいただきました。改善案は企画書通り外部サイトのURLを埋め込むことでしたが、技術不足により修正ができず悔しい思いが残っています。
将来これは役に立ちそうだと思ったこと
自分の作った作品を先生方や学生に向けて発表し、率直な意見をもらうのは苦手意識がある人の方が多いと思います。実際私も発表の時間は何をダメ出しされるか不安でいっぱいでした。しかし自分が本気で向き合った作品に素直なフィードバックを受けた結果、もちろん嫌な気持ちも無いとは言えませんが、次回はさらに良いものをつくりたいという気持ちの方が大きかったです。これは私が楽しみながら作品を作り、自分が満足できるような作品を自信を持って発表したからだと思います。すでに気に入っている作品なのにまだ改善点がある、つまりより良くできる余地があると思うと、次へのモチベーションにつながることに気づきました。今後も様々なことを楽しみながら挑戦し、自信をもって取り組みたいです。
授業で学んだことを所属学科での学びにどのように活かすか
副専攻は主専攻の学びを拡張させるための手段を学ぶことができます。今回作ったアプリは、ユーザーにクイズを通して絶滅危惧種の動物について説明し、興味を持ってもらうことが目的です。私の所属している環境システム学科での知識を活かしたものを作りたいと思い、このテーマを選びました。環境システム学科での授業で度々言われていますが、環境問題における課題は、人々の意識の低さや環境教育の不足だと思っています。今回の制作物のようにゲームで知ってもらえるようにするなど、環境について広く知ってもらうきっかけづくりができそうだと思いました。
これから授業を受ける方へ「遠慮なく自分が楽しめるものを制作していってほしい!」
私は写真が趣味で、自分が撮った写真を見て欲しいという思いがありアプリ内で動物の写真を使用しました。このように、ただ受け身でこなしているだけではただの面倒な課題ですが、いかにして自分の好きなものと融合させられるかでモチベーションが大きく上がると思います。他の授業と違い、副専攻の授業は自由度が高い課題が多いです。そのため、遠慮なくどんどん自分が楽しめるものを制作していってほしいです!楽しめば楽しむほど勝手に知識もついてくるという、かなりお得すぎる授業だと思っています。

