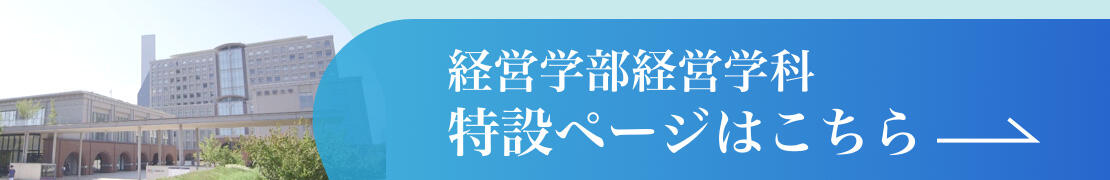- 学びのキーワード
#経営学
#社会科学
#マーケティング
#経営戦略
#経営組織
#ESG経営
#エリアマネジメント
#イノベーション
#ビジネスモデル
#組織心理学
#人材マネジメント
#財務会計
#流通経済
#中小企業経営
#経済政策
高い倫理観と広い視野、経営学と社会科学の知識と技能を備え、変転著しい現代において、自己や世界の幸せに向けて貢献できる人材を育成する。
有明キャンパス
2つの特長
経営学の理論と実践が響き合う学び
武蔵野大学経営学科のカリキュラムは、経営学の理論を単に学ぶだけでなく、それらを将来的に社会で実践するための準備ができるような内容となっています。一般的な大学の経営学科で学べるようなマーケティング・経営戦略・経営組織・財務会計等の基礎的な科目群に加えて、理論的な知識をアウトプットにつなげる際に必要な調査研究の手法に関する授業も多く設置されています。また、経営学の最先端の応用・実践分野として近年注目を集めるESG 経営やエリアマネジメントに関して学ぶこともできます。経営学の理論とその実践方法を学んだ上で、大学卒業後の自分自身のキャリアを戦略的に考えるためのキャリアマネジメント科目群が重視されていることも、私たちのカリキュラムの特長の一つです。
学生・教員・社会が共に響き合う学び
武蔵野大学の経営学科では、学生・教員・社会などが共に響き合い、学び合えるような学び方を特長としています。例えば、経営学科には、学科生同士で学び合えるようなグループワークやグループディスカッションの機会が数多くあります。200 名以上が受講している授業でも、教室で積極的に意見交換や議論を行います。また、実務の第一線で活躍しているビジネスパーソンをゲストスピーカーとして招いたり、ビジネスの現場を実際に訪問するフィールドワークを行ったりといった、実社会とのつながりの中で学ぶ授業も多々存在しています。コロナ禍で教育のオンライン化が進行しつつある中で、一緒に学び合える人々が側にいるからこそ体験できる学び方が大切だと、私たちは考えています。
学科の特長の詳細を見る
カリキュラム

経営学科は、「経営学と社会科学の知識と技能を活用して、自ら事業を経営したり、さまざまな組織において事業や組織をたすけたりすることができる人材」の育成を目指して、経営戦略・経営組織・マーケティングといった経営学の中核的領域を中心に、多様な科目を多様なカタチで学ぶカリキュラムを用意しています。
カリキュラムの詳細を見る
学生の声
経営戦略の楽しさに出会った。
身に付けた論理的思考力や分析力を社会で活かしたい
萬谷 実由
4年 広島県立廿日市高等学校(広島県)出身
幅広い学問分野をカバーする経営学科のカリキュラムに魅力を感じ、さらに高校生の頃に参加したオープンキャンパスで先生方の温かい人柄に触れたことから入学を決意しました。
入学前は、経営学や会計などの知識がまったくない自分が授業についていけるか不安でした。しかし、基礎科目が充実しており、その不安はすぐに解消しました。多様な科目を学ぶ中で、一般には公表されていない企業の戦略を考察し解き明かしていく楽しさを知り、経営戦略を深めていきたいと思うようになりました。ゼミでは「立地戦略分析」をテーマに、先生から丁寧なフィードバックをいただきながら、ある企業の店舗の周辺環境などを調査し、膨大なデータを用いて経営戦略を比較・分析する課題に取り組んでいます。
将来は、興味のある芸能マネジメント業界を舞台に、大学で学んだことを活かせればと考えています。タレントを売り出すための戦略を練るなど、これまでに身に付けた分析力や論理的に考察する力、伝える力を活かしたいと思います。
経営学科 Student’s Voice(2025年4月公開)
将来の職業イメージ
マネジメント
経営戦略や組織論を学び、企業のマネージャーを目指す
- ベンチャー企業
- 国内外優良企業( 営業・企画・人事・総務)など
企画
マーケティングや統計調査を学び、企画の専門家を目指す
企業
経営学全般を幅広く学び、起業家や事業継承者を目指す
エリアマネジメント
地域発展の理論を学び、地域発展に有益な人材を目指す
- ベンチャー企業
- 国内外優良企業( 地域発展に特化)
先輩たちの就職・進学先
タダノ/ミスミグループ本社/アキレス/アツギ/ワコール/良品計画/島忠/ぐるなび/楽天グループ/ KDDI /ソフトバンク/セラク/大塚商会/大王製紙/大東建託/大成建設/ NIPPO / 大和ハウス工業/ 東急リバブル/東建コーポレーション/スターツコーポレーション/飯田産業/全日本空輸/東日本旅客鉄道/近畿日本ツーリスト/日本郵便/共同印刷/東芝テック/セブン-イレブン・ジャパン/富士通ゼネラル/アパホテル/インテック/エイブル 他
学科長メッセージ

未曾有の時代に、経営を学ぶ志をもつみなさんへ
高瀨 央 教授
慶應義塾大学 商学部 卒業
中央大学大学院 商学研究科 博士後期課程 単位取得退学
修士(商学)
研究領域:財務会計論
私たちはいま、まさに「未曾有(みぞう)」という言葉で表現するに相応しい時代や世の中に生きていると言っても過言ではありません。すなわち、気候変動や人類を脅かすような感染症の流行、各地での軍事的緊張の高まり、さらにはAIやIoTの飛躍的な発達と暮らしへの浸透など、大きな変化や動きがある世界の中に私たちは生きています。
大きく、また、目まぐるしく変化する時代のなかで大事なことは、変わるものと変わらないもの(あるいは、変えるものと変えないもの)を見極めること、さらには、変わらないものから得られる知識や教えをしっかり身につけ、変わるものから(あるいは変えることによって)得られる利点や欠点を正しく理解することであると考えます。
企業経営においても、たとえば、経営理念のようなその企業の根幹となるような基本的な考え方や精神は容易に変えてはいけない要素である一方で、企業が扱う商品やサービスをアップデートさせる弛まぬ努力やイノベーション(企業や市場ひいては社会全体における革新的な変化)を生み出すための取り組みも企業の存続や発展には欠かせないものです。
このように、「変わるもの・変えるもの」と「変わらないもの・変えないもの」の見極めと理解に重きを置くなかで、武蔵野大学の経営学科では「響創的学び」を理念(容易に変えない基本的な考え方)として掲げています。「響創」とは、音楽を奏で響かせるように、他の人の考えや行動に共鳴したり呼応したりしながら新たなものを創りあげることを意味しており、経営学科の学生が豊かで奥深い学びが行えるように、さらには、生涯にわたって学ぶ意欲をもち続けられるように、さまざまなひと・もの・こと、そして、過去・現在・未来を響き合わせて物事に取り組む姿勢を涵養したいと考えています。
この「響創的学び」の理念を反映させたものとして、経営学科では「机上の学び」と「臨場の学び」の響創を重視しています。ここに机上の学びとは、「教室であるいは机に向かって教員や教科書から学ぶこと(何かを知ることを目的とした学び)」です。一方、臨場の学びとは、「教室外であるいは現場を体験し、頭と身体を動かしながら学ぶこと(知り得た知識や技能を実践することを目的とした学び)」です。机上で学ぶ理論や概念は現実の世界の見え方を奥深くしたり経験の質を高めたりする点で、また、実践の場で得られるさまざまな経験や現実は学問の世界に豊かさと彩りを与えてくれる点で、これら2つは学びの両輪をなすものであると考えています。
仕事をしたり企業を経営したりするうえでは、「仕事に必要なことは会社に入って学ぶから、別に大学で教わる必要はない」とか「ビジネスや経営は理屈じゃなくて経験だから、大学での勉強は役に立たない」といった、経験を重視する議論や主張をするひとも少なくありません。「経験やそこで生じる失敗から学ぶ」ことも人生においては重要であり、そのような議論や主張にも一理あります。しかし、だからといって、「大学での勉強(机上での学び)は不要/役に立たない」かどうかは別問題です。経験することは大事ですが、個人の経験というのはどうしても狭く偏ったものになってしまいがちです。また、経験や失敗から学ぶというとき、さまざまな経験を積んだり何度も失敗したりするためには、人間に与えられた時間(人生)は短すぎます。
これらの問題を脱するために便宜なものが、机上の学びです。たとえば経営学の理論や概念は、これまで先人たちが数多く行ってきた企業や組織の経営における成功と失敗の事例やそこから得られる知見を縮約し、再構成したものです。このように、机上の学びを通して、私たちが日常の生活や経験、あるいは身近なひとたちからは学べないような種類や範囲の知を得ることができます。
経営を学ぶ志をもったみなさんと、机上の学びを通して「知る楽しみ」や臨場の学びを通して「わかるよろこび」をともに分かち合えることを、教員一同楽しみにしています。
教員紹介
武蔵野大学の経営学科の教員と学生は、ゼミナールを重視しています。学生は複数回の選考を経て、最終的に1つのゼミナールに必ず配属されます。
各ゼミナールの詳細については「経営学科ゼミ一覧」をご覧ください。
経営学科ゼミ一覧の詳細を見る
教員の研究者情報の詳細につきましては「武蔵野大学 研究者情報」をご覧ください。
武蔵野大学 研究者情報の詳細を見る