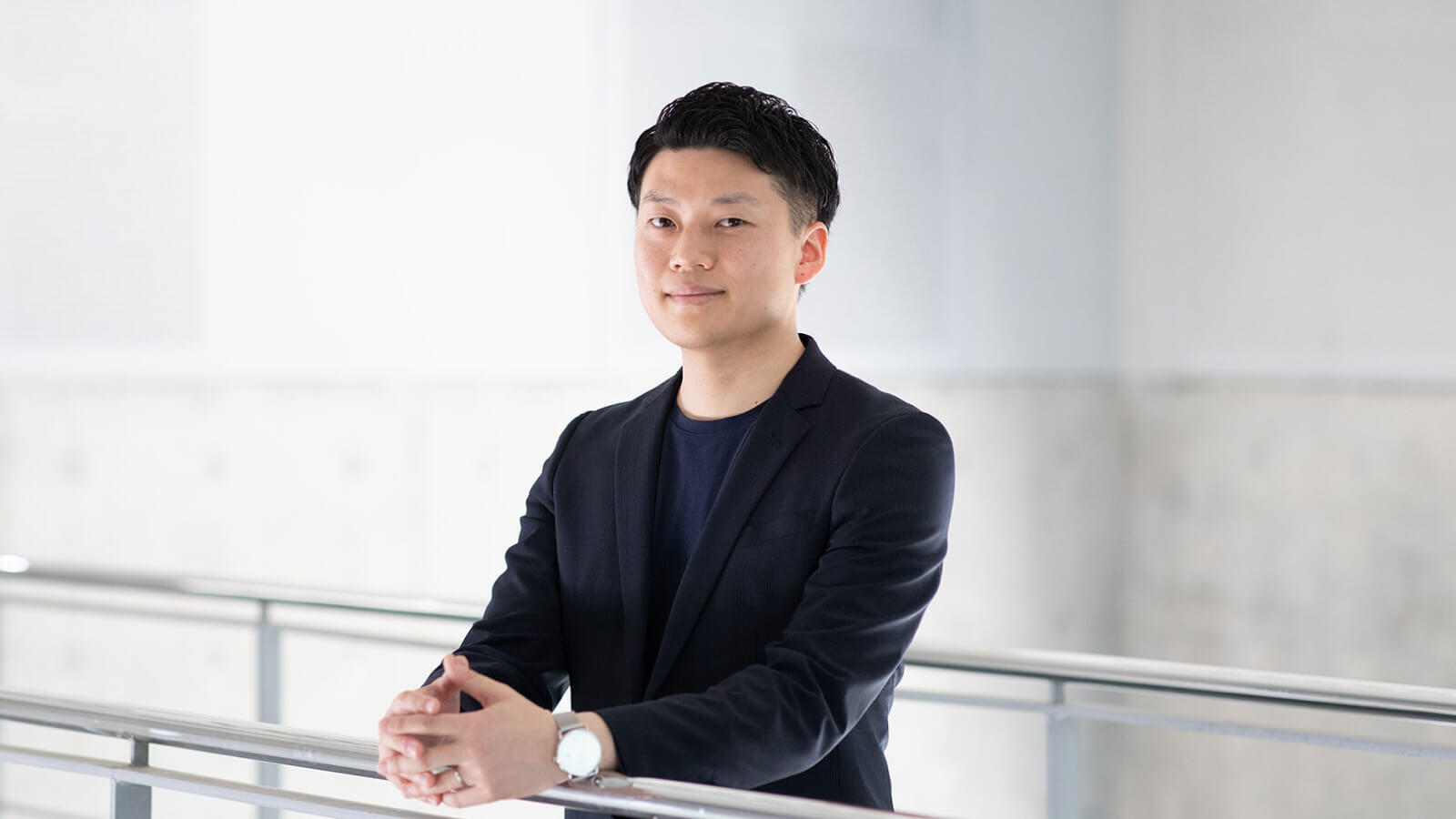- 学びのキーワード
#建築設計
#都市デザイン
#ランドスケープ
#インテリア
#家具
#製図
#建築史
#住居学
#構造
#CAD・CG
#景観論
#都市防災
建築分野において、持続可能な社会構築に向けてデザインできる専門的能力を活用して、現代社会が直面する多様な課題を解決できる人材を育成する。
武蔵野キャンパス
2つの特長
「スタジオ」「ゼミ」で専門性を高め、 全員が一級建築士を目指せるカリキュラム
建築の設計課題に取り組む「スタジオ」、社会の課題に向き合い探求する「ゼミ」を軸に、建築デザインの力を身に付けます。「スタジオ」では、1 年次に図面・模型など表現の基礎を身に付け、2・3 年次に用途・規模・敷地条件など変化に富んだ設計課題に取り組みます。「ゼミ」では、進学・就職など卒業後を見つめ、社会に貢献できる力を培います。そのほか、さまざまな講義や演習を通して、全員が一級建築士を目指せるカリキュラムです。さらに本学大学院修士課程では学部のカリキュラムと有機的につながり、より発展的な課程を用意しています。
学年・大学という垣根を越え、 「プロジェクト」を通して社会とつながる
本学科の特色あるカリキュラムとして、教員毎の専門性を活かし、多様なテーマを掲げる「プロジェクト」があります。1 ~ 4 年生が学年を越えて一丸となり、自分たちの作品や研究成果を社会に提示する活動です。チームで取り組む活動に4 年間関わるチャンスがあるところに、一般の建築系大学カリキュラムとの違いがあります。各種コンペや作品展などにも盛んにチャレンジし、実績を残してきました。個人で取り組む「スタジオ」とグループワークの「プロジェクト」が、表現力や創造的思考力を磨き、課題発見する視点、解決への実践的行動力を高めます。
学科の特長の詳細を見る
カリキュラム

1年次
「基礎ゼミ」では、卒業後の自身のキャリアを思い描きながら、建築デザイン学科の4 年間の学びを概観します。「空間表現論」や「住居論」などの授業で建築の基礎を固めます。
2年次
「設計製図」や「構造力学」「建築計画」など、学びがより専門的になります。「プロジェクト」では学年を越えて、先輩後輩と課題の制作に取り組んでいきます。
3年次
1・2 年次に身に付けた知識を活かし、建築やデザインに対する理解を深めます。専門分野を一層幅広く学び、演習やプロジェクトなどの授業では主体的に活動を行います。
4年次
3・4 年次のゼミを通し論理的思考力を鍛えます。そして、4 年間の集大成となる卒業研究・卒業制作に取り組みます。
カリキュラムの詳細を見る
5年一貫プログラム対象
学生の声
地域課題を解決するような空間をデザインし、
人々の生活を豊かにする建築物を設計したい
森谷 玲香
4年 北海道帯広三条高等学校(北海道) 出身
幼少からインテリアや建物に興味があり建築の道へ。個人で取り組む授業だけではなく、学年の垣根を超えたグループで取り組む授業があるなど、さまざまな授業スタイルで実践的に学べるカリキュラムに魅力を感じて、この学科を志望しました。
「設計製図」という授業では、先生や仲間たちと意見交換を行いながら、さまざまな設計課題に取り組みます。集合住宅が課題の際には、敷地調査や地域住民へのヒアリングを行った上で設計に取り組み、学内講評で高い評価をいただくことができました。これらの学びを通じて、地域が抱える課題を解決するような空間を設計したいという気持ちが強くなりました。建築の世界では自分がどのような設計を意図しているのか、図面やコンセプトをまとめたボードを使ってプレゼンテーションを行う場面に幾度も遭遇します。これらのさまざまな経験の積み重ねにより、説得力のある提案に必要な伝える力や分析力を伸ばすことができたと感じています。
卒業後は、より幅広い用途の建築物を設計できる実力をつけるために、大学院で専門性を深めたいと思います。将来的には、ゼネコンや建築事務所で経験を積み、地元に貢献できる建築に携わるなど、自身のプロジェクトを持ちたいと考えています。
建築デザイン学科 Student’s Voice(2025年4月公開)
取得できる資格
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
- インテリアプランナー
- 商業施設士
- 一級建築施工管理技士 など
将来の職業イメージ
建築
- 建築設計事務所
- 建設会社
- 地方自治体の都市開発・建築部門(公務員)
- ハウスメーカー
- その他建築関連会社
- 大学院進学
空間デザイン
- インテリア デザイン事務所
- 店舗企画・開発会社
- 家具メーカー
- リノベーション関連会社
- 照明メーカー
- 大学院進学
デジタルデザイン
先輩たちの就職・進学先
進学
武蔵野大学大学院/東京工業大学大学院/慶應義塾大学大学院/早稲田大学大学院/芝浦工業大学大学院/明治大学大学院 他
就職
大成建設/清水建設/大和ハウス工業/ JR東日本建築設計事務所/大東建託/東京電力ホールディングス/ NTT都市開発ビルサービス/東建コーポレーション/生和コーポレーション/住友林業ホームテック/ジョンソンコントロールズ/ LIXIL 住宅研究所/コクヨ/丹青社/三菱地所プロパティマネジメント/大気社/三栄建築設計/一条工務店/国土交通省/東京消防庁/品川区役所/八王子市役所/茨城県庁 他
卒業生の声
教員メッセージ

少し先の未来の都市や建築、空間のことをとことん真剣に考えましょう
金 政秀 教授
早稲田大学大学院 創造理工学研究科
建築学専攻 博士課程修了[博士(工学)]
研究領域:建築環境工学、建築設備
建築デザイン学科のブランドビジョンは「武蔵野の青い空、手で、足で、醒めた頭で、今日も建築まみれ」。青い空の下、緑豊かな武蔵野キャンパスは建築家、伊東忠太先生が初期のマスタープランに顧問として参画、その一角にある「実習棟」が学びの拠点。ここで、本学科の特徴である1~4年次の学生が一緒に学ぶ「プロジェクト」などが行われています。実習棟はとても小さな建物、2階から1階を全て見渡せる空間構成で、教員と学生の距離が近く、また女子学生が比較的多い中で、学際的な場として今日も建築にまみれています。
教員メッセージ

研究成果が社会に役立つ手応えを実感できる学問です
伊村 則子 教授
日本女子大学大学院 人間生活学研究科
生活環境学専攻 博士課程修了[博士(学術)]
研究領域:地震防災、 防災教育
私の専門は、学校や地域を対象とした防災教育です。防災には、建物の耐震化を進める、耐火性の強い建材を選ぶ、災害に強いまちをつくるなどハード面も大切ですが、安全なところで寝るようにする、災害時の連絡方法を決めておく、家具のレイアウトに配慮するなど、生活面においても防災の視点が必要です。なかでも重要なのは、子どもたちへの防災教育。私のゼミでは市民教育を扱っており、これまで小学生と幼稚園児向けの防災教材づくりをしました。指導する上で心がけているのは、社会還元につながる研究にすること。そのため、学生たちは、教材を制作する前に、小学校の先生や幼稚園の先生、保育士の方にヒアリングをするなど、実用的な教材づくりに取り組みました。フィールドに出て、頭・手・足を動かし、試行錯誤を繰り返しながら完成させた教材。これを実際に学校や地域で使ってもらうことで、学生たちは、研究成果が社会に役立つ喜びを実感し、学びのやる気につなげています。世の中に貢献できる学問の魅力と手応えを、皆さんにもぜひ感じてほしいと思います。
教員メッセージ
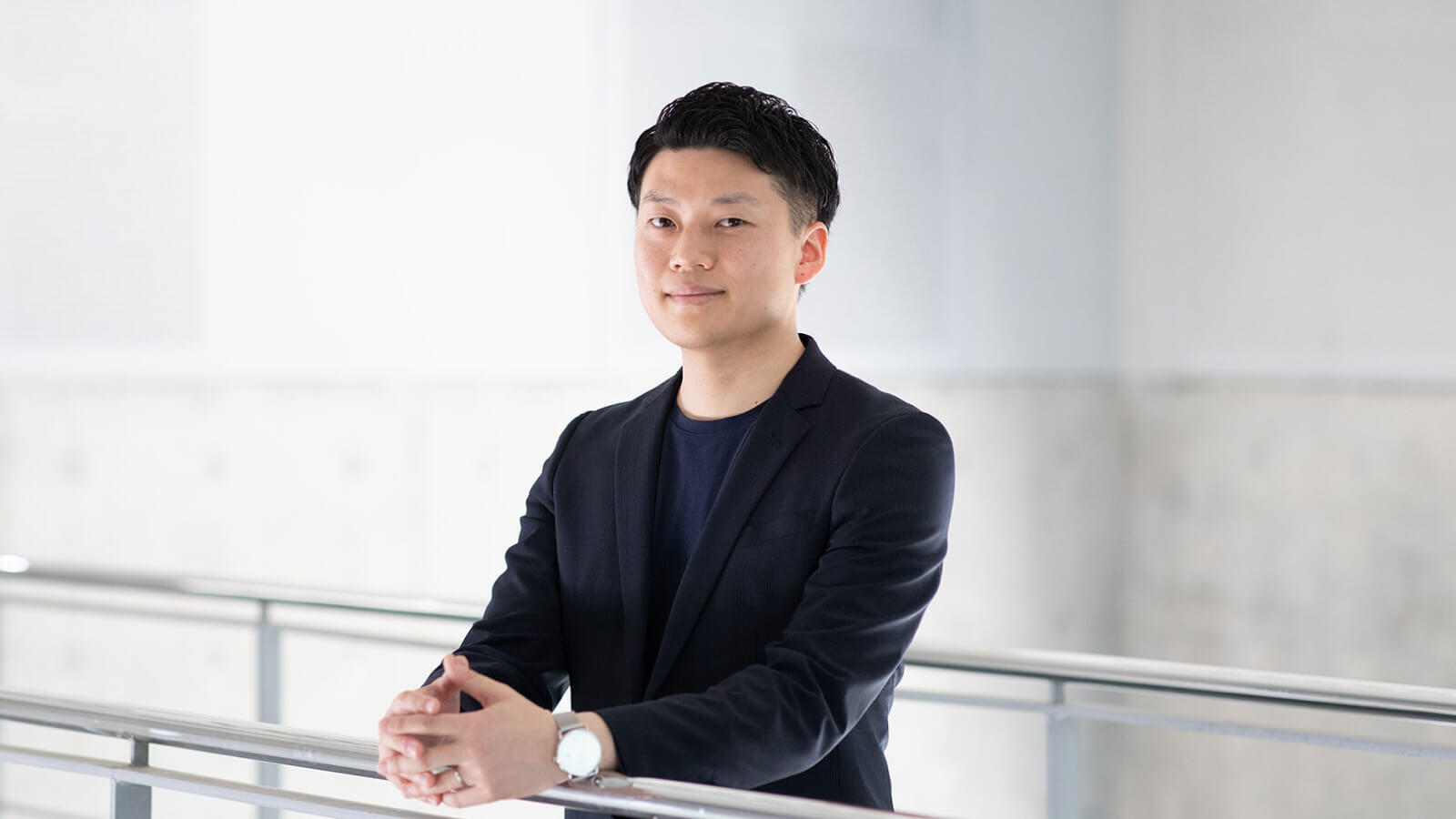
人間―環境系を育み未来をカタチにする実践知を学びましょう
太田 裕通 講師
京都大学大学院工学研究科建築学専攻
博士後期課程修了[博士(工学)]
研究領域:建築・都市計画、デザイン学
不確実性が高く、多様な価値観に溢れる現代社会において、私たちは今ある世界を「あたりまえ」だと見做してしまわず、一度距離を置いてじっくりと建築・都市のあり方を考えることが重要ではないでしょうか。建築デザインでは、今ここにある人間と環境の関係性、場所に固有なポテンシャル、人々の多様な認識を読み取り、それらを未来に紡ぎ、「ありうべき」一つのカタチにする建築的思考が鍛えられます。そもそもデザインには唯一の正解はありません。実際の状況に身を置き、問題自体を問い直したり、対話によってアイデアを共有・鍛錬し、集団で実装したり、身体的・実践的な知を駆使してより良い未来の提案を試みます。これは建築に関わらず、これからの時代に不可欠な学びの一つです。
教員紹介
教員紹介の詳細を見る


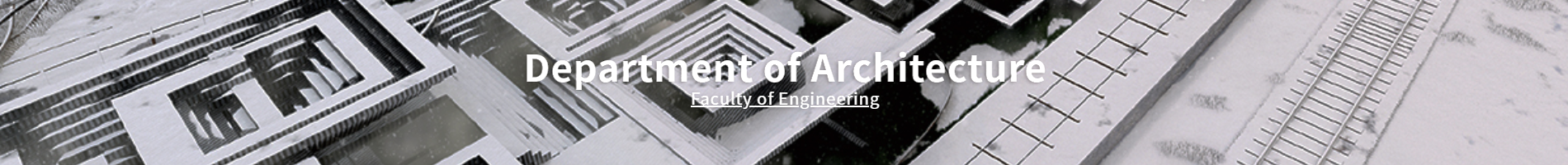 https://www.musashino-u.ac.jp/environment/design/
https://www.musashino-u.ac.jp/environment/design/