
第66回 国際政治学・アフリカ 法学部 政治学科 中村 宏毅 准教授
「最後のフロンティア」アフリカと日本の関係深化をめざして

法学部 政治学科 准教授
明治大学文学部フランス文学科卒業。パリ政治学院修士課程修了(国際機構論)。パリ第一大学研究修士課程修了(アフリカ学)。パリ第一大学政治学研究科博士課程修了。博士(政治学)。早稲田大学非常勤講師などを経て、2022年4月より現職。在フランス日本大使館専門調査員、在南アフリカ日本大使館任期付き職員として外交の現場に立った経験を持つ。専門は外交政策、国際政治、アフリカ政治。
近年、国際関係において重要な位置を占める「グローバルサウス」の国々。中でもアフリカは国の数が54カ国と多く、経済や政治などさまざまな領域で存在感を増しています。各国がアフリカ諸国との関係強化に乗り出す中、日本はこれからアフリカの国々とどのような関係を築き、発展させていくことができるのか、外交官の実務経験を生かして検討を進める中村准教授の研究を紹介します。
研究の背景
アフリカは今世界で大人気
アフリカは「人類最後のフロンティア」といわれ、その大きな潜在力に世界中が注目している地域です。貧困、紛争、難民といった課題はあるものの、2000年代以降コンスタントに経済成長を続け、人口も右肩上がりで増えています。日本人の平均年齢は50歳に近付いていますが、アフリカの平均年齢は20歳前後と非常に若く、多くの消費者を抱える市場としてこれからの成長が期待されています。経済的側面だけでなく、国際的な意思決定でもその動向が注目され、関係を深めようとする国々の間でアフリカはまさに今「引っ張りだこ」の状態にあります。

アフリカの成長は日本にとっても大きなチャンスです。1993年以降、日本政府主導のアフリカ開発に関するフォーラム「TICAD(アフリカ開発会議)」が開催され、今年8月には9回目の会合が横浜で開かれました。しかし、現地での日本の存在感は残念ながら大きいとはいえません。こうした状況を踏まえ、国際政治や外交において日本がアフリカとより緊密な関係を築くため、進むべき方向性や日本の独自性を生かした方策について研究を進めています。
研究について
アフリカで日本が存在感を発揮するために
-“派手”な援助に隠れてしまう日本の支援-
アフリカでは近年、中国やロシアの主張が浸透し、欧米諸国やG7への反発が強まっています。ウクライナ侵攻が始まった2022年2月以降、国連では繰り返しロシアを非難する内容の決議が採択されていますが、国連加盟国の4分の1以上を占めるアフリカの多くの国が棄権や欠席を選択し、あらためて反欧米の傾向が浮き彫りになりました。
背景にはいくつかの事情があるのですが、中国とソ連は冷戦中からアフリカに関与してきた歴史があり、社会主義的な考え方に共感する土壌があったこと、特に南部アフリカの国々は第二次世界大戦後の独立運動で中国やソ連の支援を受けていたことなどが影響していると考えられます。さらに最近、セネガルやコートジボワールといった元々欧米寄りの国々でも、若年層を中心に「貧困の原因は旧宗主国のフランスにある」という意識が広がり、親ロシアに流れる動きが見られます。
現在アフリカでは、フランスやイギリス、アメリカ、中国、ロシアに加え、資源や市場を求めてインドやトルコなど新興国の進出も激しさを増しています。そうした国々に比べると、アフリカでの日本の存在感は限定的です。もちろん日本はアフリカでODAによるさまざまな支援を行い、JICAの海外協力隊をはじめ多くの人が教育、農業、医療などの分野で人々の暮らしをサポートしてきました。そうした地道な貢献を評価してくれる人も一定数いるのですが、他国に比べると支援の規模が小さく、同じアジアの中国が国会議事堂やサッカースタジアムの建設といった“派手”な援助を行う中、どうしてもその陰に隠れてしまうという現実があります。
アフリカ諸国は今日の国連外交などで重要な位置を占め、アフリカと日本がより良い関係を築くことは、日本が目指す国連の安保理改革の推進にも直結します。経済的プレゼンスが低く、旧宗主国のような文化的なつながりも持たない不利な状況であることは確かですが、アフリカ諸国との関係緊密化は、これからの日本が外交力を向上させるために取り組むべき重要な課題に位置づけられると考えています。
-海洋安全保障への貢献に活路-
アフリカの国々とより緊密な外交関係を築くため、もう少し「価値」に重きを置いた外交を進めるべきと考えています。価値観外交とは、民主主義などの普遍的価値に基づいた外交を意味するのですが、特に法の支配に基づいた秩序ある国家運営や国際関係の構築という日本の価値観は、アフリカの人々に訴求する力を持つと考えています。
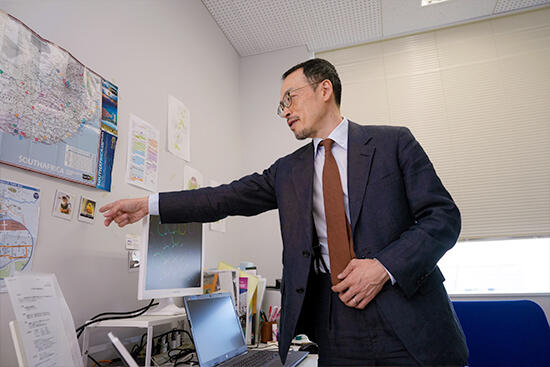
価値観外交は、言葉だけでなく、価値観を具体的な援助の形で示すことが重要ですが、私が具体的援助としてポテンシャルを感じるのは、海洋安全保障への貢献です。アフリカの沿岸諸国では今、海賊や密漁による被害が深刻化しています。日本は2009年、海賊対策のため北東部のジブチに自衛隊の拠点を構え、2024年度にはOSA(政府安全保障能力強化支援)の枠組みで沿岸監視レーダーシステムなどを供与しました。法による秩序という日本の価値観と重なるこうした貢献は、アフリカのほかの沿岸国でも評価される可能性が高いと考えています。大西洋に面したセネガルには、魚の炊き込みごはんのような「チェブジェン」という名物料理があるのですが、フランスの新聞によると、密漁の影響でチェブジェンに使う魚が獲れなくなっているといいます。日本の援助でまたチェブジェンが食べられるようになった、ということになれば、一般の人にも日本をアピールする良いきっかけになりそうです。
先ほどもお話しした通り、今アフリカでは欧米やG7への反発が高まり、中東情勢でもガザ地区やイランに対するイスラエルの攻撃に、多くの人々が怒りを露わにしています。G7の国々がイスラエル寄りの立場を取る中、G7で唯一、イランを攻撃したイスラエルに批判的な声明を出したのが日本です。欧米ともロシアとも異なる立場から法を尊重する日本の姿勢は、今後アフリカで存在感を高める推進力になるかもしれません。
今後の展望
実務家視点で関係発展の道を探る
アフリカの人口増加は今後も続き、2050年には世界の人口の4分の1をアフリカが占めると予想されています。少子化に歯止めがかからず、すでに人口減少社会に突入している日本が、勢いを増すアフリカの国々とどのように付き合っていくのかは、今後さらに重要な外交課題になると考えています。民間企業の進出をどのように後押しするかはもちろん、逆にアフリカの企業や人をいかに日本に呼び込むか、人的交流の拡大発展という観点からも興味を持って研究していきたいと考えています。

また、元外交官ということもあり、日本の国際的な地位向上には常々関心を持っています。G7の中でも、イギリスやフランスはかつてアフリカを植民地化した歴史があり、言葉や文化の繋がりがある反面、負の感情を持つ人もいます。しかし歴史的な関わりが薄かった日本にはそうしたわだかまりがなく、比較的主張が受け入れられやすいという点は、日本の強みと考えることもできます。そうした強みを活かして、民主主義国としてどのようにアフリカ諸国との関係性を発展させていけるのか、実務家視点で追究していくことを目指しています。
教育
外交官の経験を生かし学生の視野を広げる
担当している「外交政策論」「アフリカ政治論」「平和学」などの授業では、常に最新の情報を取り入れ、私の外交官としての経験を盛り込みながら話すよう心掛けています。その際は、起きたことを話題にするだけでなく、それらの出来事がどのような歴史的背景を持っているかを解説し、多面的な見方や深い理解に繋げています。
また、アフリカやヨーロッパについて取り上げるときは、音楽、文学、食など、各国の文化も積極的に紹介しています。たとえば、南アフリカに関する講義では、ワインの生産が盛んであることを出発点に、ワインの生産技術を持ち込んだのは宗教改革による迫害から逃れて移り住んだユグノー派のフランス人たちだったことを紹介し、さらに近世フランスの歴史や南アフリカの歴史にも話題を広げています。

ODAに対して「遠くの国の支援より国内にお金を使った方がいい」と考える学生もいます。日本の財政状況が厳しくなる中で、そのように考える学生もいるのは理解できるのですが、もう少し広い視野も持って欲しいと思っています。例えば、南アフリカに囲まれたレソトという国があり、日本は、中等学校の整備や食料援助を行っています。在南アフリカ大使館はレソトを兼轄しているので、私もよく出張に行ったのですが、実際に現地でレソト外務省職員に話を聞くと、その支援が高く評価されていて、「日本は友好的な国だ」と国際選挙などの場での日本支持に繋がっていました。こうした実体験を交えながら、外交手段としてのODAの有用性などを伝え、学生の外交や国際政治に対する理解を促しています。
人となり
フランス文学専攻からアフリカの専門家へ
今は外交やアフリカ政治が専門ですが、大学時代の専門はフランス文学でした。高校時代、教科書でアルベール・カミュの「シジフォスの神話」を読んで、カミュを勉強したかったんです。4年間仏文で勉強して、カミュとサルトルの比較をテーマに卒業論文を書いたのですが、サルトルの思想を入口に政治学に興味がわいたので、大学卒業後、パリ政治学院の修士課程に留学しました。そこで一番関心を持ったのが国際政治学の分野です。特に世界の不均衡への問題意識から途上国のことをよく知りたいと思い、フランスと歴史的に繋がりの深い途上国としてアフリカを研究し始め、研究修士課程はパリ第一大学のアフリカ研究科に進みました。さらに、パリ第一大学の博士課程に進学し、博士課程在学中にフランスの日本大使館でアフリカ担当の専門調査員になり、そこから外交の実務経験が始まっています。
人生を変えた南アフリカでの5年間

博士号を取得した後、今度は在南アフリカ大使館で任期付き職員として働くことになり、5年間南アフリカのプレトリアで暮らしました。よく学生に「南アフリカって暑いんですよね?」と聞かれますが、今の日本の夏の方がよほど暑いです(笑)。乾期の半年間はカラッと晴れて過ごしやすく、ワインもビールも牛肉も安くておいしい。今も1年に1回程度は南アフリカに行きますが、いいところですよ。

南アフリカにいる間ハマっていたのがサファリツアーです。プレトリアから車で5、6時間のところにあるクルーガー国立公園へ行って、朝早くからサファリカーで動物を見て、池のほとりで夕日を眺めながらビールを飲み、夜はブライと呼ばれるバーベキューをして、公園内の宿泊施設でライオンやハイエナの声を聞きながら寝るんです。基本的に危ないことはないのですが、宿泊施設から出たらそこにいたジェネットという動物とばっちり目が合って、お互いその場で2、3秒固まったりしたことはありました。

南アフリカでは、ネルソン・マンデラの故郷である東ケープ州を歩いて巡るツアーに参加したことも思い出深いですね。東ケープ州は、南アフリカの中でも貧しい地域で、電気や水道が通っていない村もありました。そこで暮らす人々の生活に触れたことは、人生の中で大きな経験として心に刻まれています。自分が大きく変わる経験ができました。
読者へのメッセージ

日本のみなさんにとって、アフリカは遠くにあって馴染みがなく、紛争や未発展の地というイメージが強いのではないでしょうか。しかし、実際に行ってみると想像以上に発展していますし、自然も豊かで、学術的にもとても面白い場所です。今回お話ししてきた通り、潜在的成長力を持つアフリカの国々は、外交、経済などさまざまな面で日本が協力関係を築きたい相手でもあります。ぜひみなさんにもアフリカの国や人々に関心を高めていただきたいですね。
取材日:2025年7月

