
第70回 ウェルビーイング学・創造学 アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科 芝 哲也 教授
デザイナーの思考法から世界を幸せにするイノベーションを

アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科 教授
デザイン事務所Cauz(コーズ)代表。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程修了。バンクーバー・フィルムスクールデジタルデザイン学科卒業後、カナダの大手広告代理店に勤務。帰国後、デザイン事務所NOSIGNERでサイエンスコミュニケーションや災害支援など社会課題解決プロジェクトに参加し、2011年デザイン事務所Cauzを設立。クリエイティブ思考協会代表理事、日本ブランド経営学会理事。ディチャーム株式会社 訪問美容サービス「Charmful」にてGood Design賞受賞。
技術の進歩や価値観の変化に伴い、今、社会のさまざまな場所で求められている「イノベーション」。デザイナーとして自ら事務所を構えて活動する芝教授は、自身の経験をもとにイノベーションを起こす発想力やクリエイティビティを鍛えるメソッドをまとめ、社会人や学生への教育にも力を注いでいます。ウェルビーイングとイノベーションを掛け合わせ、「世界の幸せをカタチにするイノベーション」の創出を目指す芝教授の本学での取り組みを紹介します。
研究の背景
デザインができなかったからデザイナーに
私は19歳の時、デザイナーの太刀川英輔さんの影響でデザインの道に足を踏み入れました。日本の専門学校でデザインやプログラミングの基礎を学んだ後、カナダのバンクーバー・フィルムスクールに進み、卒業後は現地の広告代理店BLAST RADIUS(ブラストレディアス)での勤務も経験しました。2011年に設立した自分のデザイン事務所では、ウェブ、グラフィック、映像などのデザインはもちろん、街づくり、中小企業の支援、起業家支援、社会課題解決などへのデザインの適応を得意としています。

デザインのようなクリエイティブな活動は「才能の世界」だと思われ、どうすればできるようになるのかという“コツ”がそれほど一般化されていません。私自身、あまり器用な方ではなく、デザインという分野に出合った当初は「世の中にこんなに難しいことがあるのか」と感じ、「どうすればできるようになるのか知りたい」という動機でデザイナーになることを決めました。日本やカナダで勉強し、仕事をする中で、実体験から見つけた“アイデアを形にするコツ"や研究の成果をまとめ、10年ほど前から慶應義塾大学、アントレプレナーシップ学部の発足からは本学で学生の教育にも携わっています。
研究について
デザイン思考を応用してアイデアを形にしやすく
武蔵野大学では、大きく分けて「デザイン」「ブランディング」「イノベーション(新規事業開発)」の3つの専門性を活かして授業を行っています。
今、社会ではどんな業種でも、アイデアを出すこと、アイデアを形にすることが求められています。それを呼吸をするように行うことができるのが、デザイナーです。彼らの目的はアイデアを形にすることですから、その過程を科学的に捉えて体系化しようとはあまり考えないのですが、その体系や技術を一般化できれば、誰でも説明や訓練を受けることでデザインやクリエイションができるようになるはずです。
世の中にはすでに、デザイナーやエンジニアが考えるように思考し、課題解決を図る「デザイン思考」「システム思考」といった思考法があります。しかしそれらは直感的ではなかったり、効果が表れにくかったりするところがあると私は感じています。そこで、デザイナー以外のクリエイターの思考プロセスなども取り入れて、デザイン思考を拡張、深化させたメソッド「クリエイティブ思考」をまとめ、アイデアを形にできる可能性を高める方法、課題解決やイノベーションを起こす方法を学生に伝えています。
ブランディングと哲学
―「なぜ存在しているのか」を明確に―
私の専門性の一つに、ブランディングがあります。ブランディングと聞くと、日本では「他社との差別化を図ってモノを売るために行うこと」というイメージが強いのではないでしょうか。しかし海外では、ブランディングとは「この組織はなぜ存在しているのか」を明確にするためのものとして捉えられています。新規事業をつくる際、自分たちが何を目標としているのか、組織自体がどんな性格や人格を持っているのかをはっきりさせると、たとえば製品をどんなデザインにするのか、ロゴにどんな書体を使うのかといったアウトプットの在り方も決まってきます。「デザインと事業創造」という授業では、デザインに加え、そうしたブランディングの考え方も教えています。
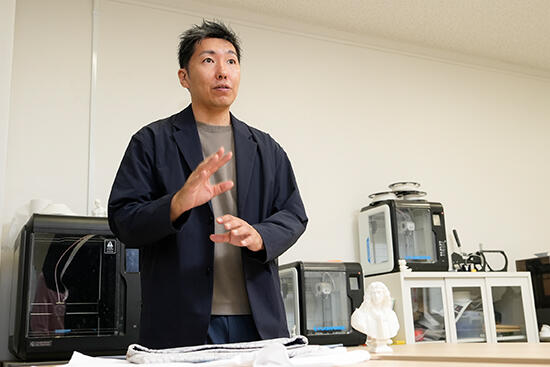
もう一つ、私が担当している授業に「事業と哲学」があります。なぜ私が哲学を教えているかというと、名前に「哲」の字が入っているから……ではなく(笑)、「そもそも自分たちはなぜ存在しているのか」を考えていくブランディングは、哲学と相通じるところがあるからです。授業では、「正しいとは何か」という哲学的な命題からスタートし、徐々に「武蔵野大学アントレプレナーシップ学部が目指すものは何か」など、学生が自分事化できる課題について考えてもらいます。最終的には学生一人ひとりが、「自分は何を大事にしていて、何が目標で、どうして生きているのか」といったことを考えて明文化し、行動につなげるサポートをしています。
―ウェルビーイングなイノベーションを―
かつて経済活動は利益を上げることだけを目的とし、組織の存在意義も個人の存在意義も考える必要はありませんでした。しかし近年、利益さえ上がればそれでいいという考え方や経済合理主義は崩れつつあります。さらにAIの利用が広がる中、私たちは「人間の仕事とは何か」という根本的な問題に向き合う時代を迎えています。そうした今だからこそ、「何を大事にして、どんな行動を取りたいか」を考える哲学、そしてブランディングを学ぶ重要性は高いと考えています。
また、私は慶應義塾大学の大学院で、本学ウェルビーイング学部長の前野隆司先生とウェルビーイングの考え方に出会いました。前野先生が提唱している「幸せの4因子」(①自己実現と成長、②つながりと感謝、③前向きと楽観、④独立と自分らしさ)は、実はイノベーションやアントレプレナーシップに必要な条件と重なります。そこで、ブランディングやイノベーションとウェルビーイングを掛け合わせ、「そもそも何を目標にするのか」「それは人を幸せにするのか」からスタートし、人を幸せにするアイデアを考え、それを形にするまでを一気通貫で教えることもしています。
今後の展望
目指すは「1億2000万個のイノベーション」

私が研究、実践、教育を通して目指しているのは「1億2000万個のイノベーション」です。1億2000万、つまり日本人全員が一人1つイノベーションを起こすことができれば、もっとウェルビーイングな社会を実現することができます。幸せの4因子とイノベーションに必要な要素が重なっているのですから、すべての日本人が誰かを幸せにするためにイノベーションを起こすと、自分自身も幸せになり、社会もウェルビーイングに変わっていくはずです。イノベーションは、1年で起こすのは難しそうですが、30年もあれば何とかなりそうな気がしませんか? 今や人生100年時代ですから、生涯で3回はチャンスがある。そう考えると、私には「1億2000万個のイノベーション」は実現可能なものに見えるんです。
日本から1億2000万個イノベーションを起こし、いずれは地球全体で70億個のイノベーションを目指す。そのためのアントレプレナーシップ学部であってほしいし、武蔵野大学であってほしい。そんな思いで、貴重な「イノベーションを起こしてくれる人材」である学生への教育に全力以上の力で取り組んでいるところです。
教育
ゼミでデザインフェスタに出展
ゼミには、デザインそのものを学びたい学生と、デザインやブランディングを知ることでビジネスを広げたい学生が集まり、実践的な学びを展開しています。今年は、ブランディングから商品開発、製造、販売までを一気通貫で経験するため、学生がオリジナルのブランドをつくり、東京ビッグサイトで開催された「デザインフェスタ」に出展しました。自分たちがデザインしたアクセサリーやTシャツ、手ぬぐいなどを作って販売したのですが、実はなかなか売れなかったんです。それは、彼らがプロダクトを作ることに精一杯で、売るための接客や陳列、マーケティングにまで頭が回っていなかったから。初めての出展だったので先の見通しが立ちにくく、時間が足りなかった面はあるのですが、売るためのマーケティングもデザインのうちです。新規事業は「千三つ」、つまり1000作っても3つうまくいく事業があるかどうか、と言われ、いくら良いものを作ってもそれが伝わらなければないのと同じ。今回の出展を通して、イノベーションとマーケティングの重要性を実感してもらえたのではないかと思っています。
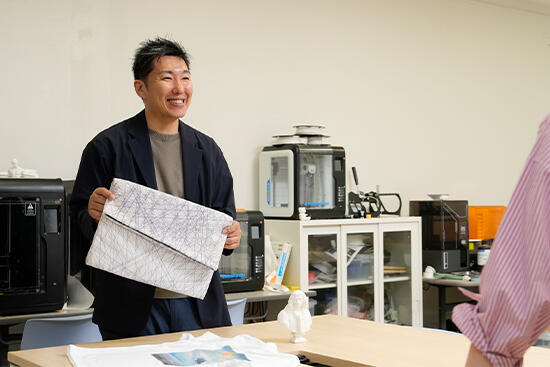
学生とは、上下関係というより、ちょっと上の先輩くらいのイメージで関わっています。カナダでの学生時代、30ぐらい年上の後輩がいたのですが、周りのみんなが同い年くらいの感覚でうまく付き合っているのを見て以来、私は「30歳を過ぎたら同い年理論」を唱えていました。そして、最近娘が生まれたことにより、「人類皆同い年理論」へと変わりました。20年ほどデザインの研究や実践を続けているので、学生に伝えられることはそれなりにあるのですが、上の立場から教えるというより、学生が本当にやりたいことを見つけたり形にしたりするお手伝いをしている感覚です。
人となり
生活に潤いと驚きをもたらす3歳の娘

今、一番の趣味は「娘」です。娘が生まれてから、日々の生活の潤いがすごく増えました。3歳になる娘は本当に創造性が高くて、「その発想はなかった!」という方向で遊びを提案してきたりするので、見ていて感動します。「我々はどこでこの創造性を失ってしまうんだろう」とつくづく思います。たとえば、通っているリトミックの教室で娘が急に、先生が提案するプログラムを「やりたくない」と言い出したことがありました。ちょうどほかの子がいないクラスだったので、先生もそれを受け止めてくださって、娘が自分で1時間分のプログラムを決めることになったのですが、驚いたことにちゃんとつくったんですよ。しかも、彼女の中には1時間の流れがちゃんとあって、まずこの動きをして、次にボールを使う動き、その次は花火みたいな動き、その後オオカミをやっつけに行く、みたいなストーリー性のあるプログラムだったんです。びっくりしましたけど、面白かったですね。
19歳から修行したカンフーと酔拳
19歳の時にデザインに出合いましたが、同じ時期にもう一つ出合ったものがあります。「カンフー」です。
個人的な意見ですが、男はみんな19歳ぐらいの時に必ず格闘技を志すものなんですよ。それを素直に実行に移したのが私です。格闘技をいろいろ探していく中で、一番美しい動きをしていたのが、カンフーの先生でした。その先生の道場に通い始め、そこで「酔拳もある」と聞かされて、3年ほど酔拳の修行をして全部の型を学びました。カンフーが面白いのは、おじいちゃんでも強そうなところ。女性も強そうですよね。その「力ではなく技術」の感じが良いんですよね。カンフーとは「練習・鍛錬・訓練の積み重ね」という意味です。そのあたりはおそらく私のデザインの教え方のベースにもなっていて、「練習して積み重ねれば誰でもできるはず」という考え方も、どこかスポーツ的なんじゃないかなと思っています。





読者へのメッセージ

アントレプレナーシップは一般的に「起業家精神」と捉えられていますが、私たちは「新しい価値を生み出すマインド」だと考えています。人間の仕事の一部がAIに置き換えられる時代にあって、新しい価値を生み出すクリエイティビティは今後どの分野、どの業種でも必要とされます。アントレプレナーシップ学部で、学生と一緒に、これからの世界で必要になる大切な力を育んでいけたらと思っています。
取材日:2025年9月
- アントレプレナーシップ学部 アントレプレナーシップ学科
https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/entrepreneurship/entrepreneurship/

