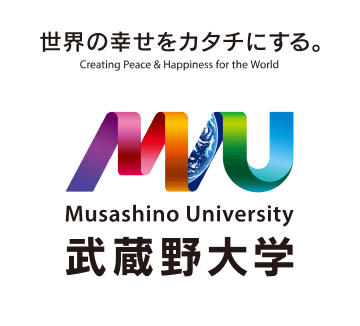第20回 臨床心理学人間科学部 人間科学科 中島 聡美 教授
悲しみに沈む心に寄り添う治療を届ける

人間科学部 人間科学科 教授
中島 聡美Satomi Nakajima
筑波大学医学専門学群卒業。筑波大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。専門は精神医学、被害者学、臨床心理学。常磐大学コミュニティ振興学部助教授、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所成人精神保健研究部犯罪被害者等支援研究室長などを経て、2018年より現職。武蔵野大学認知行動療法研究所長。
犯罪被害や災害は、人の心身にとても大きな衝撃を与えます。誰もが混乱し、強い不安を感じます。このような反応は異常な状況に直面したことで生じる人間の正常な反応であり、時間の経過とともに和らいでいくことも多いのですが、一方、強い恐怖や不眠、不安が続き、心的外傷後ストレス障害(posttraumatic stress disorder, PTSD)やうつ病のような精神疾患をきたす場合も少なくありません。またこのような出来事で大切な人を失った遺族では悲嘆が長期に続く「複雑性悲嘆(遷延性悲嘆症)」も見られます。そのような人々に対する心理療法の開発や効果検証に取り組み、臨床の現場でケアや治療を実践する中島聡美教授の研究をご紹介します。
研究の背景
犯罪被害者や遺族の心理的ケア
1996年、当時勤務していた常磐大学で被害者支援センターの設立に関わることになったのを機に、精神科医として犯罪被害者の心理的ケアや支援に取り組むようになりました。その前年には阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件が起こり、日本でもトラウマやPTSDの問題が少しずつ注目され始めた時期です。しかし、まだ精神医学や心理学の領域でも被害者支援はマイナーな分野で、誰かが治療やケアをしなければ、という強い思いを抱いたことが、この分野を専門にしたきっかけの一つです。本学の副学長であり、当時から被害者支援に力を尽くされている小西聖子先生が大学院の先輩だったことにも後押しされて、被害者や遺族が抱える精神的問題の病態と治療の研究を始め、現在は犯罪被害や自死などの遺族に多くみられる複雑性悲嘆の治療の開発と効果の検証を中心に研究を行っています。
研究について
複雑性悲嘆の日本版治療プログラムを開発
-何年も悲しみが続く「複雑性悲嘆」-

複雑性悲嘆とは、大切な人を失ったりした時の悲しみが長期にわたって緩和されず、対人関係や社会生活に支障をきたしているような状態をいいます。 家族や親しい友人を亡くして、悲しんだり気分が沈んだりする。それ自体は自然なことで、もちろん病気ではありません。仏教ではお葬式から1年経つと一周忌の法要がありますが、ちょうどそのくらいの時期になれば、多くの人は悲しみが和らぎ、元の生活に戻っていきます。しかし複雑性悲嘆は、そうした通常の悲嘆に比べて悲しみの感情が非常に強く、「何年経ってもお葬式の日と同じくらい悲しい」「亡くなった方への思いにとらわれて社会生活が立ち行かない」といった状態になってしまうのです。特に犯罪被害、災害、自死の遺族に多く見られ、2019年にはWHOの疾病分類であるICD-11で「遷延性悲嘆症(prolonged grief disorder)」という精神障害に位置づけられました。
日本での調査研究では、死別を経験した人の2.4%が複雑性悲嘆の状態にあると報告されています。昨年日本で亡くなった人は、約145万人。その数倍の遺族がいると考えれば、「2.4%」は決して少ない人数ではないでしょう。しかし、それほどたくさんの人が苦しんでいる問題でありながら、複雑性悲嘆の専門的な治療や支援は、まだほとんど行われていません。この状況を何とかしたいと考え、コロンビア大学(米国)のキャサリン・シア(Sher, K.)先生が開発した複雑性悲嘆の治療プログラム(complicated grief treatment, CGT)を日本に導入し、有効性を検証する研究を始めました。
-喪失の悲しみに向きあうことに寄り添う-

複雑性悲嘆は、通常の悲嘆のプロセスが、さまざまな要因でストップしている状態だと考えることができます。CGTは、その「要因」に焦点を当て、正常な悲嘆のプロセスに導いていく治療です。たとえば、家族の死があまりもショックで現実として受け止められていない方が多いのですが、この治療では、亡くなった時に立ち返って、繰り返し語ることで、徐々に死の現実と向き合えるようにしていきます。悲しい経験を思い出すのはつらいことですが、それを繰り返していくうちに、次第に大切な人の死の経験が自分の人生の記憶に組み込まれ、回復へと向かっていくのです。また、悲しみに向きあうだけでなく、大切な方を大事にしつつも、自分自身の生活に希望や夢をもつことも促していきます。アメリカで開発されたこの治療法を、日本で普及しやすいプログラム(日本版複雑性悲嘆治療,J-CGT)に改良し、本学の認知行動療法研究所で臨床研究を行っているところです。
また、CGTを元にしたオリジナルの悲嘆の集団認知療法「ENERGY(Enhancing Natural Emotional Recovery for Enduring Grief and Yearning: 悲しみとともに生きる)」を開発し、その効果検証も進めています。ENERGYは、少し症状の軽い複雑性悲嘆の方や、通常の悲嘆であっても苦痛の著しい方を対象にしたグループセラピーです。CGTは精神科医や公認心理師が行う専門性の高い治療ですが、ENERGYは、保健師や看護師の方も行えるプログラムで、災害後の地域や緩和ケア医療などさまざまな場所で実施できることを目的としています。
-悲嘆を複雑化させる「コロナ禍の死」-
この2年間、世界は新型コロナウィルス感染症の蔓延に苦しんできました。コロナ禍における死は、遺族の悲嘆を複雑化させる可能性が非常に高く、今後、ケアや治療を必要とする遺族が増えるのではないかと危惧しています。
コロナ禍では、高齢者施設や病院で面会が制限され、多くの家族が看取りをすることができませんでした。特に感染拡大初期、新型コロナが原因で亡くなった方の遺族は、ご遺体と対面することさえ叶わず、自宅に戻ってくるのは火葬された後という、通常の死別とはあまりにも違う状況に置かれました。突然そうしたお別れを余儀なくされた遺族には、強い罪悪感が残り、悲嘆のプロセスが正常に働かなくなる方が増えることも予想されます。コロナ禍の中で親しい人を亡くした方へのケアには、もっと目を向ける必要があると考えています。
臨床でPTSDや犯罪被害者の治療も

複雑性悲嘆の研究のほか、PTSDの治療研究、犯罪被害者のメンタルヘルスや治療に関する研究にも継続的に取り組んでいます。 複雑性悲嘆が遺族の方が抱える問題であるのに対し、PTSDは被害に遭ったご本人が抱えてしまう問題です。1990年代半ばに私が被害者支援に関わり始めたころ、日本ではPTSDに対する有効な治療法がなかったため、米国で開発された持続エクスポージャー療法(prolonged exposure therapy, PE)を日本に導入して効果を検証する研究に関わるようになりました。現在は、同じくPTSDに対する治療法の一つである認知処理法(cognitive processing therapy, CPT)の効果研究にも関わっています。どちらの治療法も、まだ日本で受けられる場所は少ないのですが、本学では心理臨床センター、認知行動療法研究所でPEやCPTの臨床活動を行っています。

▲犯罪被害者のメンタルヘルス情報ページ:http://victims-mental.umin.jp/
武蔵野大学心理臨床センターのHP(https://www.musashino-u.ac.jp/rinsho/)から入ることができます。
今後の展望
治療法の普及と臨床家育成に取り組む
複雑性悲嘆は、世界的に見ても、その概念自体がまだ一般的ではありません。病理や治療の研究に取り組む研究者が少ない分野である一方、先にもお話したとおり、有病率が2.4%と非常に高い疾患でもあります。今後、J-CGTやENERGYについて無作為化比較試験を行い、有効性をはっきりと示すことで、治療現場への普及に繋げたいと考えています。
現場への普及という点では、人材育成も大きな課題です。複雑性悲嘆もPTSDも、精神科のクリニックなど一般の臨床では基本的なケアも難しい状況にあります。専門的な治療ですから、治療法を身につけるには大変な労力が必要ですし、治療者を育成する指導者も不足しています。私も研修やスーパーヴィジョンを行っていますが、本学のセンターを基盤に臨床家の育成をさらに進め、少しでも多くの方が治療を受けられる環境をつくっていきたいと考えています。さらに、専門的な心理療法に関心のある臨床家が、大都市に偏っているという問題もあります。個人的には、都道府県単位でトラウマなどを扱う拠点病院をつくり、そこで臨床家を育成、サポートする仕組みを作ることで地域偏在を解消できるのではないかと考えています。

一般の方への研究の紹介という点では、過去にNHKの「あさイチ」で複雑性悲嘆とその治療について取り上げる回があり、私も出演させていただきました。最近では、精神科の看護師が主人公の漫画「こころのナース夜野さん」(水谷緑、小学館『月刊スピリッツ』で連載中)で複雑性悲嘆とその治療が取り上げられました。こうした作品などを通して、被害者支援や悲嘆に対して少しずつ社会的な理解が広がることを願っています。
教育
心理療法の実績豊富な本学ならではの学びを

学部では、精神医学、心理実習、司法・犯罪心理学などの授業を担当しています。本学には、トラウマや犯罪被害者、心理療法を専門とする先生が数多く在籍し、心理臨床センターや認知行動療法研究所は、トラウマの治療では日本で最も臨床経験のある心理療法センターと言っても過言ではないと思います。学生には、そうした環境だからこそできる学びを体験し、確かな知識を身につけてほしいと考えています。 さらに、知識を身につけるだけでなく、ぜひ「大学生らしい学び」をしてほしいですね。大学は、既に分かっていることを理解する場ではなく、まだ分からないことを主体的に追究していく場です。まずは自分が何に関心があるのかを知り、それについて疑問を持ち、専門書や文献を使って理解を深める力をつけることができるよう指導しています。また、せっかく人間科学科で学ぶのですから、人間の心理について深く考え、人間の存在そのものを客観的な視点でとらえるとともに、人の心の痛みを理解する経験もしてほしいと思います。その経験が、今世界が直面している多様性や偏見の問題に向き合う力になり、人の尊厳や価値性を見直すことにも繋がると思います。
人となり
人の尊厳や心を支える仕事をめざして
人の心や心のケアに興味を持ったのは、中学生くらいのころだったと思います。きっかけは、当時話題になっていた灰谷健次郎さんの本。『兎の眼』や『太陽の子』を読んで人の尊厳や心を支える大切さを感じ、いつか自分の仕事にできたらいいなと思っていました。当時は臨床心理士という職業がなく、「人の心を支える仕事」としてイメージしやすかった仕事が、精神科医だったんです。どうしても精神科医になりたくて、本当は血を見るのが大嫌いだったのですが、大学では医学部に進学しました。
大学在学中、児童思春期の専門医である稲村博先生(故人)が行っていた不登校児のキャンプでボランティアを経験して刺激を受け、思春期・青年期が専門の精神科医を目指すようになりました。不登校や社会不安症、ひきこもりになった子どもの治療やケアには、投薬治療だけでなく、傾聴や支持、家族アプローチなどの心理的ケアが求められます。そこで心理療法への関心や学びを深めたことが、現在の研究領域に結びついています。
止まらない「ペンギン愛」

小さいころからペンギンが大好きなんです。友人にもらった世界各国のペンギングッズであふれる私の研究室は、「ペンギン御殿」と呼ばれています。 好きになった時のことは今でも覚えていて、たまたま見ていたテレビの南極特集で、氷に覆われた真っ白な大地に1羽のペンギンがピンと立っている映像を見て、その雰囲気が何とも言えず「いいな!」と思ったんです。子どものころは、ペンギンの研究者になりたいと気持ちも少しだけあったのですが、調べてみたら南極に着くまでにすごく荒れる海域があることが分かって、車酔いする私には無理だな、と諦めました(笑)。
オーストラリアに、野生のペンギンが海から巣に帰る姿をすぐそばで観察できる有名な島(フィリップ島)があって、学会でメルボルンに行った時、学会後に念願叶って観察ツアーに参加することができたんです。小さなフェアリーペンギンがぴょこぴょこ歩くのを、ペンギンを驚かせないようにただただ黙って見守るという、それだけのツアーなんですけど。もう至福の時間でしたね。仕事をリタイアしたら、南極大陸でペンギンを見るツアーにも行ってみたいです。
―読者へのメッセージ―

臨床でトラウマの治療に携わっていると、子どもの頃の体験が人生に及ぼす影響の強さを感じずにはいられません。子どものころに虐待を受けた経験は、その後の人生で、PTSDやうつ病を含めさまざまな疾患や障害のリスクになり得ます。一方で、ひどいトラウマを受けても不思議なほど心が健康でいられる人もいるのですが、そうしたレジリエンス(回復力)を持つ人たちの多くは、周囲の人に愛されていると感じながら子ども時代を過ごしています。子どもが「自分の存在に価値がある」「自分は愛されていて幸せだ」と感じられる社会、レジリエンスを育む環境をつくっていくことがいかに大切かを、今私たちはあらためて考え、行動していく必要があるのではないでしょうか。
取材日:2022年2月