武蔵野大学スマートインテリジェンスセンター(MUSIC)
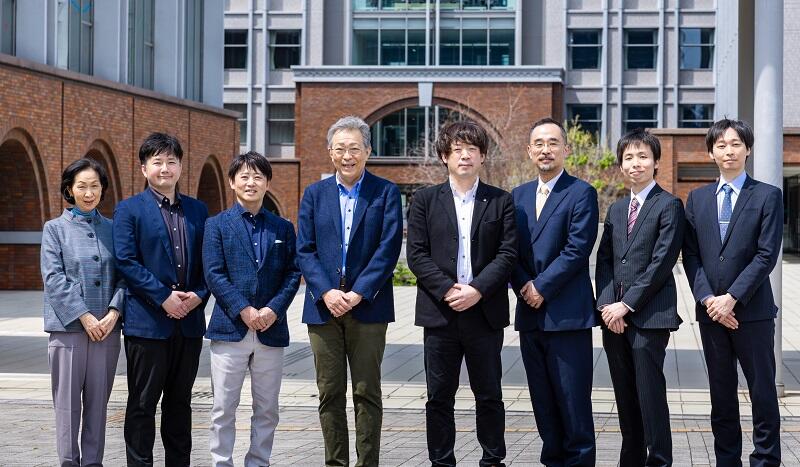
仕事できるにもほどがある
ここ数年の生成AIの進化と普及によって、多くの仕事が激変しています。人間にしかできない創造的な仕事と言われてきた、イラスト作成、広報宣伝、プログラミング、同時通訳、ビジネス企画、等々多くの現場で人間より遙かに速くアイデアを出してくれるようになったからです。これから大学で学び、社会に出て行く準備をすることになる皆さんは、将来への不安の中で、どの学校のどの学科で何を学ぶのが正解なのか、迷い悩んでいるのではないでしょうか。
これまでは頼りになっていた優良企業や一流大学といった序列も、社会の先輩方の経験知も、もはや当てにはなりません。企業も大学も先輩方も、例外なく変化の渦に飲み込まれていくからです。
今こそ、落ち着いて考えてみるときです。ハルシネーションという言葉があります。生成AIが出してくるもっともらしいけれども誤っている回答のことを指します。AIが内容を理解せずネット上で流れている無数の発言から、表層的に回答を作り出しているために起きる現象です。
では、だれがAIの回答の誤りに気付いているのでしょうか? それはその分野を表層でなく深く理解している人です。そうした人たちだけがAIの誤りを正し、その力を最大限に活かせるのです。特定の分野の高い専門性とAIを活用できる力を併せ持つ人たちが活躍する未来がそこにあります。

武蔵野大学スマートインテリジェンスセンター (MUSIC)は、AIが日常になった時代に活躍できる人材を世に送り出すために作られました。
私がこの大学で教壇に立つようになったのはほんの数年前からです。それまでは、ITコンサルティング会社の社長としてビジネスの現場を見てきました。私の持つ実践性と大学の先生方の持つ専門性が出会うことで、これまでにない教育の場、MUSICが誕生しました。
私たちは、いくつもの常識を覆してきました。ひとつは学部学科の壁。
MUSICが主管しているAI副専攻コースはどの学科でも学ぶことができます。当然、文系理系の区別もありません。AI活用でもっとも大切なのは理数系の能力などではないのです。
そして、教員が学生に知識を教えるという一方通行性も過去のものにしました。絶え間なく進化するAIと社会を、教員もまた学び続けます。学生と共に。しかしより深く本質を。
共に学ぶことで学び方を学んでもらうことこそが、変化に追随する唯一の方法だということです。私たちと一緒に新しい時代を切り拓いていきませんか?
MUSIC スタッフ紹介
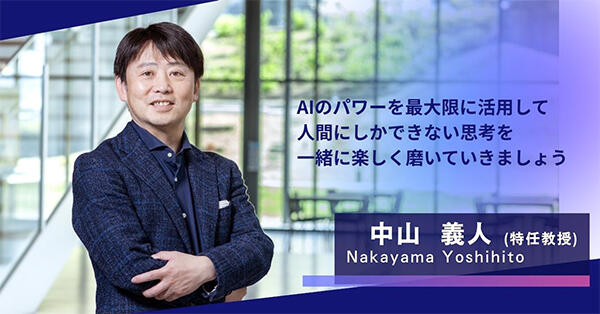




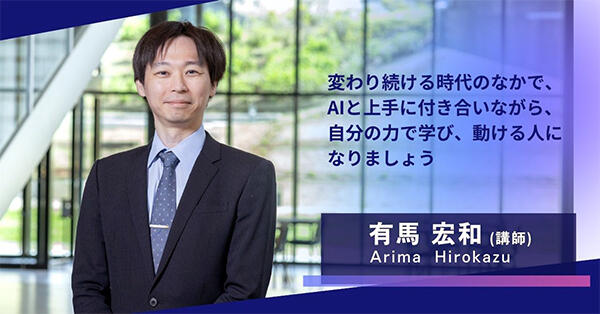
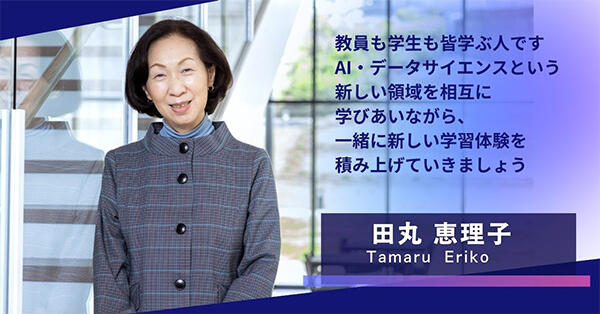
実績(MUSIC研究成果・紀要)
メディア掲載
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年 11月7日(木) |
星川 真菜(環境システム学科4年) 渡邊 紀文(MUSIC) |
大学の副専攻でPepperを使ったサービスを開発、コンテストでの入賞経験が就職活動の武器に! | 「STREAMチャレンジ2024」で特別賞を受賞した、AI副専攻1期生の星川真菜さん(環境システム学科4年)のインタビュー記事が、ソフトバンクロボティクスの導入事例として紹介されました。 | ソフトバンクロボティクス株式会社HP人型ロボットPepper(ペッパー)導入事例 |
| 2 | 2025年 1月19日(日) |
野田 彩乃(経済学部経済学科3年) 渡邊 紀文(MUSIC) |
Pepperを利用した高齢者向けのサービス『高齢者の見守りサポートするPepper』で「2024年度STREAMチャレンジPepper部門」決勝大会で入賞! | Pepperのコンテスト「2024年度STREAMチャレンジPepper部門」において、AI副専攻2期生の野田彩乃さん(経済学科3年生)が、「人工知能実践プロジェクト」の授業で作成した、Pepperを利用した高齢者向けのサービス『高齢者の見守りサポートするPepper』決勝大会で入賞を果たしました。 | 2024年度STREAMチャレンジ<Pepper部門> |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 8月12日(土) |
新川 大海(日本語コミュニケーション学科3年) | ベネッセ主催の「User-Based Digital Competition」にて最優秀賞受賞 | ベネッセ主催のUser-Based Digital Competitionで、副専攻1期生の新川大海君が最優秀賞を受賞した。新川君が企画および開発し、本人からも「副専攻で学んだことが大いに役立った」とのコメントももらっている。 | User-Based Digital Competition (主催:ベネッセコーポレーション) |
| 2 | 2023年 11月5日(日) |
副専攻(AI活用エキスパートコース) 1期生 林 浩一(MUSIC) |
生成AI、大学の授業で活用法探る 試験対策やキャリアデザインにも | 対話型AI(人工知能)を、リポート作成などとは違う形で活用しようという授業が大学で行われ始めている。試験対策や就職への活用も視野に、様々な模索が進む。公務員試験の時事問題対策、教育で活用も。 | 朝日新聞 2023年11月5日(日)教育24面 朝日新聞デジタル 2023年11月5日(日) |
| 3 | 2023年 12月3日(日) |
林 浩一(MUSIC) | 授業に生成AI、思考育む | 大学が授業での生成AI(人工知能)活用を拡大している。日本経済新聞の調査に回答した520校のうち3割が活用を始めた。就職後をにらんでAIを使いこなす力を育てる動きが目立つ。 | 日本経済新聞 2023年12月5日(火) 朝刊3ページ 日本経済新聞(nikkei.com) 2023年12月2日(土) |
| 4 | 2024年 3月17日(日) |
星川真菜(環境システム学科3年) |
「STERAMチャレンジ2024<ロボット部門>」において、「君の隣にPepper:利用者に寄り添った日常会話で夜道の不安を緩和するPepper」で特別賞を受賞 | STREAMチャレンジ2024において、AI副専攻1期生の星川真菜さん(環境システム学科3年生)の「君の隣にPepper:利用者に寄り添った日常会話で夜道の不安を緩和するPepper」が、人とロボットの新しい関係を提案できたということで評価され、特別賞を受賞しました。 | STREAMチャレンジ2024(主催:超SDGsラボ、共同主催・運営:ソフトバンクロボティクス株式会社) |
| 5 | 2024年 3月29日(金) |
林 浩一(MUSIC) | データサイエンティスト・ジャパン2024にてMUSICセンター長林教授が基調講演を行いました | データサイエンティスト・ジャパン2024にてMUSICセンター長林教授が基調講演「データサイエンス「活用力」を身に付けたAI-readyな学生を社会に送り出す」を行いました。 | データサイエンティスト・ジャパン2024(主催:日経クロステック、協力:日経コンピュータ) |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 3月17日(金) |
渡辺 杏奈(環境システム学科 2年) | アニメブームで繋ぐメディア芸術 | 様々な漫画のアニメ化が進んでいる中で、アニメ化されるか否かについて、何が影響を与えているのかについて、分析した。アニメ化との関連性の高い特徴量として、マンガタイトルと掲載数、平均/開始位置割合、雑誌タイトル、掲載開始日(年)、合計掲載ページ数であることが導かれた。第3回メディア芸術データベース活用コンテスト 最優秀事例。 | 第3回メディア芸術データベース活用コンテスト(主催:文化庁) |
| 2 | 2022年 4月11日(月) |
武蔵野大学 | 「副専攻AI活用エキスパートコース」で「kintone」を導入した新しいDX推進人材の育成 | 武蔵野大学(東京都江東区)は、AI時代のDX人材育成のための「副専攻(AI活用エキスパートコース)」にて、2022年4月より、サイボウズ株式会社が提供する業務アプリ構築クラウドサービス「kintone」を採用した授業を開講しました。 | 学校法人武蔵野大学プレスリリース |
| 3 | 2022年 11月2日(水) |
林 浩一(MUSIC) 大坪 璃音(環境システム学科2年) |
ビジネス現場に求められるDX人材の育成に向けた大学の新たな挑戦~データ分析や業務アプリ構築まで、授業の学習基盤となったkintone | kintoneを活用した「情報技法発展B」と呼ばれる科目では、データを活用して業務課題の論理的解決とDXを学ぶということをテーマに掲げており、企業から許諾された数万件にも及ぶリアルデータを活用し、実際のビジネスシーンで活かせる業務改善提案スキルを学んでいく。 | サイボウズ社公式Webページ |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 掲載メディア 登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 10月11日(月) |
渡邊 紀文(MUSIC) | 【武蔵野大学】国内私立大学として初導入! エンタープライズAIプラットフォーム「DataRobot」を活用した『AI人材育成プログラム』 | 機械学習活用およびデータサイエンス活用などの授業科目、また人工知能実践プロジェクトにおいて、DataRobotを導入したことのPRとその経緯について説明 | PRTIMES |
学会発表
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年 6月1日(日) |
宮田 真宏(MUSIC) 木口 春花(環境システム学科4年) 田丸 恵理子(MUSIC) |
複数視点映像を用いた店舗内における感情状態変化の抽出の試み | 本発表では,複数視点で記録された映像に対してAIによる分析をすることで小売店舗滞在中の顧客の感情状態を時間的・空間的変化を可視化する手法を提案・評価した.結果,強い感情変化は店舗の空間的特徴と関連し,さらにか解釈可能であることを示唆する結果を得た. | 第219回ヒューマンインタフェース学会研究会(主催:ヒューマンインタフェース学会コラボレーション基盤専門研究委員会) |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年 8月11日(日) |
宮田 真宏(MUSIC) 進藤 匠(教育学科) 田丸 恵理子(MUSIC) |
AI技術を用いた模擬授業振り返り支援システムの検討 | 教員養成段階の模擬授業に着目し、その際の学生の振り返りのための手法について検討した。ここでは、生成AIを用いたコメントシートの分析と計測技術による半自動的な場面分類の現状について報告した。 | 情報教育シンポジウム2024(SSS2024) |
| 2 | 2024年 8月23日(金) |
中村 太戯留(MUSIC) | ハピネスを可視化する活動を通じた学修意欲の向上に向けた取組 | 「自分ごと」として学びの内容を認識して学修意欲を高める活動を実施した。具体的には、受講生自身に関するハピネスを数値化し、学びの対象となる人々と比較対照しながら可視化してもらった。課題の記載文字数において底上げ効果や天井上げ効果が見られ、自分と学びの対象を比較対照することの有効性が示唆された。 | 2024年度ICT利用による教育改善研究発表会 (主催:公益社団法人私立大学情報教育協会 ) |
| 3 | 2024年 9月7日(土) |
有馬 直輝(日本文学文化学科3年) 田丸 恵理子(MUSIC) 宮田 真宏(MUSIC) |
リフレクト機能を用いた学生の感情状態把握の試み | 本研究では、Microsoft社のリフレクト機能を活用し、学生の感情状態を活動ごとに収集・可視化した。授業形態や文理による感情の違いを分析し、感情状態と授業内容の関係を明らかにすることを試みている。また、教員が授業を振り返る際の活用可能性についても検討している。本発表では、対象授業での観察結果や分析内容を報告し、教育現場での実践に向けた示唆を提供した。 | 日本教育工学会2024年秋季全国大会(主催:日本教育工学会) |
| 4 | 2024年 10月12日(土) |
大山 瑞貴(人間科学科3年) 鈴木 大助(北陸大学) 宮田 真宏(MUSIC) |
オンライン授業中のグループワークにおける心理的安全性が学生の行動に与える影響 | オンライン授業中にグループワークをしている大学生の心理的安全性に着目し、グループワーク中の発言回数などの定量情報と事後アンケートによる定性情報との関係性を分析した。結果、アイスブレイクの必要性やリーダーの存在の有無、時間配分の明示が重要な要素として抽出された。これを踏まえて実際に別の授業にて実践し、一定以上の効果がある結果を得た。 | 教育工学研究会(ET)(主催:一般社団法人電子情報通信学会) |
| 5 | 2024年 10月27日(日) |
木口 春花(環境システム学科3年) 田丸 恵理子(MUSIC) 宮田 真宏(MUSIC) |
複数視点映像を用いた顧客行動の可視化方法の検討 ~「過ごす店舗」に焦点を当てた分析~ | AI副専攻の授業にてデータ提供いただいている伊東屋横浜元町店の店舗で実際に実験を行い、被験者の行動経路や滞在場所の可視化、行動理由等の分析結果を報告した。 | 第214回ヒューマンインタフェース学会研究会(主催:特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会) |
| 6 | 2025年 2月15日(土) |
鈴木 玲菜(環境システム学科3年) 高橋 和枝(サステナビリティ学科) 山本 浩之(武蔵野大学非常勤講師) 中村 太戯留(MUSIC) |
データサイエンスを活用して自身の暗黙的性質を見つける活動の実践事例:片頭痛の発生予測をめぐって | 機械学習ツールを用いて個人に特化した片頭痛の予測を試みた。天候データやスマートウォッチで取得した睡眠データや生体データを特徴量とし、各自の主観データである片頭痛の痛みの度合いをターゲットとした片頭痛の予測モデルを構築した。その結果として、天気予報中の用語の出現頻度との関係が示唆された。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 178回研究発表会 |
| 7 | 2025年 3月1日(土) |
宮田 真宏(MUSIC) 大川 愛梨亜(日本文学文化学科 3年) 田丸 恵理子(MUSIC) |
顔情報を用いたオンライン授業における学習困難状態推定の試み | 近年のオンライン授業の発展に伴う問題点として受講者側の状況が分からないという問題がある。本研究ではこの問題はオンライン授業中の顔の情報を分析することで解決可能であると考え、その取り組みの一つとしてAI技術を用いた顔情報の抽出と機械学習での学習可能性を検討し、顔の特徴量を用いた分類の可能性について示したものである。 | 教育工学研究会(ET)(主催:一般社団法人電子情報通信学会) |
| 8 | 2025年 3月14日(金) |
赤羽 海飛(薬学科 3年) 朝倉 大樹(武蔵野大学非常勤講師) 岡田 龍太郎(データサイエンス学科) |
機械学習AIツールを用いた実写映画化の成功予測とその要因の考察 | 漫画原作の作品に対して実写映画化が成功する要因を分析するために、多くのデータを収集するとともに、要因となりうる特徴量を定義しています。映画の成功要因の分析の先行研究としてはアンケート等の定性的な評価が主流であり、本研究のような定量的な研究は貴重なものです。 | 情報処理学会 第87回全国大会 万有知能化の世紀へ―実世界に行きわたる人工知能 |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 6月3日(土) |
宮田 真宏(MUSIC) 田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 林 浩一(MUSIC) |
広域センシング手法を用いた授業中の学生の行動可視化の試み | 武蔵野大学の提唱している響学スパイラルを実現するために作られた教室を対象にその評価にAI技術を用いることができるかについて検討したもの。発表では顔認識AIを用いた行動可視化を行い、授業の状況把握に役立つことを示唆する結果を示した。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会 170回研究発表会 |
| 2 | 2023年 6月3日(土) |
中村 太戯留(MUSIC) | クラウドツールを用いたデータ活用スキルの育成の試み | データサイエンスに関して、学生の関心を高め、適切に理解して活用する能力の育成が急務となっている。足場掛けを目的として、操作が比較的容易なデータサイエンスに関するクラウドツールを導入した。学生による授業アンケートでは、「最終課題で満足のいく結果を出すことができた」という項目に対して5段階評価の4が最頻値という結果であり、その有用性が示唆された。 | 情報処理学会 コンピュータと教育研究会170回研究発表会 |
| 3 | 2023年 8月19日(土) |
古矢 一翔(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) |
公務員試験対策のための対話型生成AI の活用 (ポスター発表) |
対話型生成AI を活用した効果的な公務員試験の対策方法について実践を踏まえて報告する。公務員試験に含まれる複数の科目に対して、対話型生成AI であるChatGPT による問題の生成と解答の生成能力を活かした効果的な学習ができるかどうかを試行した。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
| 4 | 2023年 8月19日(土) |
布施 諒一(法律学科 3年) 林 浩一 (MUSIC) |
対話型生成AI を活用したTOEIC 試験対策の一手法 (ポスター発表) |
本論文では、英語学習における生成AI の効果的な活用方法について述べる。筆者等は、TOEIC テストを対象に、生成AI であるChatGPT を用いて、学習モチベーションを向上させる勉強方法を提案する。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
| 5 | 2023年 8月19日(土) |
倉次 野恵(教育学科 3年) 江口 奈穂(教育学科 3年) 林 浩一(MUSIC) |
対話型生成AIを解答者とする作問学習による生徒の知識の活用力向上の試み (ポスター発表) |
対話型AI を解答者にした作問を通じて、作問者が自律的に問題を補正することのできる自律型作問学習を提案する。通常、児童生徒の作問した問題の解答者は、他の学生であるが、筆者等は対話型生成AI である、ChatGPT を解答者として設定した作問学習の可能性を検討している。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
| 6 | 2023年 8月20日(日) |
田丸 恵理子(MUSIC) 風袋 宏幸(建築デザイン学科) 宮田 真宏(MUSIC) 林 浩一(MUSIC) |
学生と共に教室を進化し続ける構築プロセスの実践と評価 | 武蔵野大学が提案する「響学スパイラル」に基づく授業を生み出すための新しい学習環境(響室)を構築中である。「再生」「相互作用」「学生と共に創る」を中心コンセプトに置く。今回は「学生と共に創る」構築プロセスに関して、このプロセスを授業実践として組み込むことで,構築プロセス自体もまた響学スパイラルによる学びとなり、結果として構築された学習環境だけではなく、構築プロセスを継続的に学びのスパイラルアップが可能なプロセスとすることができた。 | 情報処理学会 情報教育シンポジウムSSS2023 |
| 7 | 2023年 8月25日(金) |
中村 太戯留(MUSIC) | 作問学習による授業時間外の自主的な学修を促す試み | 反転授業として事前に配信する動画の視聴確認として作問学習を実施した。授業アンケートで、作問学習が役立ったかを5件法で尋ねたところ中央値が5で、授業外の学修時間も、前年度の「1時間~2時間未満」から「2時間~4時間未満」に改善し、その有用性が示唆された。 | 私立大学情報教育協会 2023年度 ICT利用による教育改善研究発表会 |
| 8 | 2023年 8月30日(水) |
宮田 真宏(MUSIC) 山田 徹志(玉川大) 大森 隆司(玉川大) |
顔情報を用いた授業活動の自動セグメンテーションの試み | 教室内に設置したカメラ映像を顔認識AIを用いて特徴量を抽出し、その中でも顔の検出数を用いて授業活動中のマップを作成することができることを示し,さらにそのマップの分類は機械学習手法を用いることで示した。 | 第48回教育システム情報学会全国大会 |
| 9 | 2023年 9月16日(日) |
勝山 隼斗(経済学科) 進藤 匠(教育学科) 田丸 恵理子(MUSIC) 宮田 真宏(MUSIC) |
創造的な教室空間を対象とした学習場面の分析手法の検討 | 武蔵野大学で提唱されている響学スパイラルを実現するための教室の評価を授業映像を人手で確認、記述し実際の映像に関する情報として可視化できることを示すと共に、教育学部の模擬授業を対象に、教員の発問の質を定量的に推定することを試みその結果を学生同士のアンケートや教員からのフィードバックにより確認できることを示した。 | 日本教育工学会 2023年秋季全国大会 (主催:日本教育工学会) |
| 10 | 2023年 9月17日(土) |
宮田 真宏(MUSIC) 山田 徹志(玉川大) 大森 隆司(玉川大) |
顔情報を用いた授業活動の自動セグメンテーションの評価 | 教室内に設置した4台のカメラ映像を分析することにより授業活動中のマップを機械学習を用いて作成することができることを示し、さらにその評価を複数の手法で試すことで安定した推定ができることを示した。 | 日本教育工学会 2023年秋季全国大会 (主催:日本教育工学会) |
| 11 | 2023年 11月5日(日) |
星川 真菜(環境システム学科3年) 宮田 真宏(MUSIC) 渡邊 紀文(MUSIC) |
利用者に寄り添った日常会話で夜道の不安を緩和するロボットの提案 | サービスロボットの多くは接客業務が中心であり、日常で人とコミュニケーションをとる機会はまだ少ない。本研究では、ロボットが日常会話をすることで友人関係を築き、不安を持って夜道を歩く人に信頼を与えることで不安を緩和するサービスを提案する。ソフトバンクロボティクス社のPepperに搭載されたジェスチャーや音声合成機能を利用して動作を生成し、タッチセンサーや音声認識機能を利用して人とインタラクションをする。これにより、雑談や会話の内容に適応したコミュニケーションをとるロボットを作成した。 | 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーション基礎研究会 (主催:電子情報通信学会) |
| 12 | 2023年 11月5日(日) |
安達 美月(人間科学科 3年) 宮田 真宏(MUSIC) 渡邊 紀文(MUSIC) |
ユーザーがリラックスした状態でストレスレベルを把握するためのロボットの提案 | 労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場において、年一回のストレスチェックの実施義務がある。しかし、ストレス社会に常にさらされていることや、労働者がその時期に忙しかった場合等を踏まえると、ストレスレベルを把握する機会は年一回では少ないと考えられる。そのため、いつでも気軽にストレスを把握できる機会を設けることが必要である。そこで本研究では、ユーザーが雑談などを通してリラックス状態になるように促した上でストレスチェックに臨み、気軽にストレスの状況を把握できるコミュニケーションロボットを作成した。 | 電子情報通信学会ヒューマンコミュニケーション基礎研究会 (主催:電子情報通信学会) |
| 13 | 2024年 3月7日(木) |
白川 桃子(数理工学科 3年) 宮田 真宏(武蔵野大学) 佐々木 多希子(武蔵野大学) 友枝 明保(関西大学) |
新しい文書要約手法の提案 | 私たちの身の周りは多くのデータで溢れており、その分析手法もまた多様に存在する。しかし、データに対する絶対的な分析手法は未だ確立されていない。本研究では、現代日本人が感じている大量の文書を読むということへのハードルを越えるために、独自の手法を取り入れた新しい文書要約手法を提案した。 | 第9回学生研究発表会 (主催:応用数理学会若手の会) |
| 14 | 2024年 3月7日(木) |
進藤 匠(教育学科 3年) 田丸 恵理子(MUSIC) 宮田 真宏(MUSIC) |
AI技術を用いた模擬授業の評価の試み | 今後の教員には従来以上に教育の質が求められることが予想される。この教育の質は教員養成では模擬授業にて養うことができるが、個々の受講生に合わせた指導は困難である。この問題に対して本研究では、模擬授業中の教員が児童に対して発する発問に着目し、人手による発問場面の記述とAI技術を用いた分析との関係を比較することにより、発問場面の自動的な評価を試みその結果の模擬授業の振り返りへの適用方法について検討した。 | 日本教育工学会 2024年春季全国大会 (主催:日本教育工学会) |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年 6月4日(土) |
大崎 理乃(MUSIC) 田丸 恵理子(MUSIC) | データサイエンス的アプローチを含めたサービスデザイン教育の検討 | 武蔵野大学では、サービスデザインとデータサイエンスを融合したプログラムを提供する予定であるが、サービスデザインとデータサイエンスの融合に関して、2名の教員が「サービスデザインのデザインプロセス」「デザイナーとユーザの関わり合い」の2つの立場からデータサイエンスとサービスデザインに関して論じ、その議論を踏まえた上で、どのようにサービスデザインのプログラムを提供していくべきかを論する。 | 2022年度春季HCD研究発表会(HCD-Net) (主催:特定非営利活動法人人間中心設計推進機構) |
| 2 | 2022年 8月25日(木) |
中村 太戯留(MUSIC) | 学修目標を自己チェックする仕組みによる受講生の主体性促進の試み | 学修目標を受講生が自己チェックする仕組みを用い、受講生が主体的に課題内容の質向上に取り組む手法を実証的に提案した。受講生アンケートで5段階で評価してもらったところ5が最頻値であり、その有用性が示唆された。 | 2022年度ICT利用による教育改善研究発表会 (主催:公益社団法人私立大学情報教育協会) |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 要旨 | 学会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021年 8月25日(水) |
中村太戯留(MUSIC) | オンライン授業におけるミーティングツールを活用した協調学修の促進 | 「対面授業」および「同時双方向型のオンライン授業」のどちらでも実施可能な協調学修の手法を実証的に提案した。緊急事態宣言の発出による対面授業からオンライン授業への切替に対応でき、受講生の評価も得ることができ、その有用性が示唆された。 | 2021年度ICT利用による教育改善研究発表会 (主催:公益社団法人私立大学情報教育協会) |
| 2 | 2021年 1月27日(土) |
大﨑理乃(MUSIC) 田丸恵理子(MUSIC) | 学部生を対象としたAI・データサイエンスコースにおけるサービスデザイン教育プログラムの検討 | 武蔵野大学では、サービスデザインとデータサイエンスを融合したプログラムを提供する予定であるが、サービスデザインとデータサイエンスの融合に関して、2名の教員が「サービスデザインのデザインプロセス」「デザイナーとユーザの関わり合い」の2つの立場からデータサイエンスとサービスデザインに関して論じ、その議論を踏まえた上で、どのようにサービスデザインのプログラムを提供していくべきかを論する。 | 2021年度冬季HCD研究発表会(HCD-Net) (主催:特定非営利活動法人人間中心設計推進機構) |
修了式など学内表彰
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 発表タイトル | 掲載メディア/登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年 9月9日(月) |
野田 彩乃(経済学科3年) | 高齢者の見守りをサポートするPepper | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 2 | 2024年 9月9日(月) |
牧山 詞音(経済学科3年) | 消費者の求める情報を動的に提供するECサイト | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 3 | 2024年 9月9日(月) |
伊藤 里桜(人間科学科3年) | AIは心理カウンセラーの代わりに働くことが出来るのか-AIと心理カウンセラーの共存- | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 4 | 2024年 9月9日(月) |
木口 春花(環境システム学科3年) | 「過ごす店舗」の魅力とは何か~来店時の行動と視線データによる考察~ | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 5 | 2024年 9月9日(月) |
日高 萌(日本文学文化学科3年) | 小説家になろうからみる人気作品タイトルの要素・条件分析 | AI副専攻 優秀賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 6 | 2024年 9月9日(月) |
赤羽 海飛(薬学科3年) | 機械学習を用いた実写映画化の成功予測と要因の考察 | AI教育推進機構賞-AIエンパワーメント賞- | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 7 | 2024年 9月9日(月) |
有馬 直輝(日本文学文化学科3年)
|
リフレクト機能を用いた学生の状況把握 | イノベーション賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 8 | 2024年 9月9日(月) |
鈴木 玲菜(環境システム学科3年)
|
ひとりひとりにあった偏頭痛を予測するツール | イノベーション賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 9 | 2024年 9月9日(月) |
松本 蓮(政治学科3年) | 政策に対する考えや要求に基づいて政党を提案するチャットボット | デジタル未来創造賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 10 | 2024年 9月9日(月) |
大川 愛梨亜(日本文学文化学科3年)
|
顔情報を用いた授業中の学生の「困った」分類器の開発の試み | ウルシステムズ賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 11 | 2024年 9月9日(月) |
今泉 春樹(法律学科3年) | ユーザーの嗜好を基に旅行先を提案してくれるチャットボット | paiza賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 12 | 2024年 9月9日(月) |
萬谷 実由(経営学科3年) | 顧客の購買データに基づく商品のレイアウトの検討-「銀座伊東屋横浜元町店」の万年筆の配置の最適化に向けて- | ビジネス実装して売上改善に結びつくで賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 13 | 2024年 9月9日(月) |
渡邊 康太(環境システム学科3年) | SNSの画像共通点から見るファッショントレンド予測AI | オンギガンツブレインハック賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 14 | 2024年 9月9日(月) |
榛葉 亮(経済学科3年) | 株式投資のアドバイスをおこなうチャットボット | 経済学科賞(AI) | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 15 | 2024年 9月9日(月) |
田名部 翔聖(法律学科3年) | シチュエーションや歴史を含めてスーツを提案するチャットボット | 法律学科賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 16 | 2024年 9月9日(月) |
宇津 帆香(環境システム学科3年) | 水族館は現代人にとって第三の居場所(サードプレイス)になるか? | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 17 | 2024年 9月9日(月) |
大山 瑞貴(人間科学科3年) | オンライン授業のグループワークにおける心理的安全性が学生に与える影響 | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 18 | 2024年 9月9日(月) |
岸川 遼祐(経営学科3年) | 将来的な資産運用のための投資シミュレーション | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 19 | 2024年 9月9日(月) |
窪木 里紗(経営学科3年) | プロ野球における集客率の要因と提案 | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 20 | 2024年 9月9日(月) |
齊藤 彩実(経済学科3年) | 夏でもメイクを楽しみたい!メイクアップアドバイザー | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 21 | 2024年 9月9日(月) |
鈴木 悠仁(薬学科3年) | 留年と非認知能力の関わりを探し、留年を減らす方法を提案する | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 22 | 2024年 9月9日(月) |
津留 美月(経営学科3年) | 口コミデータ分析による理想のカフェ提案サービス | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 23 | 2024年 9月9日(月) |
三橋 彩花(日本文学文化学科3年) | プラットフォームごとの視聴者を惹きつける配信内容の分析 | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 24 | 2024年 9月9日(月) |
山田 幸奈(経営学科3年) | "推し"の知名度・人気を高める,AIを活用した楽曲制作の提案 | AI副専攻奨励賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース 成果発表会・修了式 |
| 25 | 2024年 9月9日(月) |
白川 桃子(数理工学科4年) | AI副専攻貢献賞 | ||
| 26 | 2024年 9月9日(月) |
木村 歩夢(経済学科4年) | AI副専攻貢献賞 | ||
| 27 | 2024年 9月9日(月) |
小谷 菜摘(会計ガバナンス学科4年) | AI副専攻貢献賞 | ||
| 28 | 2024年 9月9日(月) |
穐本 京子(グローバルコミュニケーション学科4年) | AI副専攻貢献賞 | ||
| 25 | 2024年 10月30日(水) |
白川 桃子(数理工学科4年) | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaランク賞、paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 26 | 2024年 10月30日(水) |
高橋 ひかり(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaランク賞、paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 27 | 2024年 10月30日(水) |
宮地 沙綾(データサイエンス学科3年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaランク賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 28 | 2024年 10月30日(水) |
松尾 優里(人間科学科3年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaランク賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 29 | 2024年 10月30日(水) |
池谷 暁(数理工学科2年) | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaランク賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 30 | 2024年 10月30日(水) |
石丸 希(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 31 | 2024年 10月30日(水) |
安藤 珠理愛(薬学科3年) | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 32 | 2024年 10月30日(水) |
安田 悠矢(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 33 | 2024年 10月30日(水) |
古屋敷 伊織(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 34 | 2024年 10月30日(水) |
原田 龍馬(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 35 | 2024年 10月30日(水) |
津布久 尚貴(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 36 | 2024年 10月30日(水) |
津藤 永暉(データサイエンス学科4年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| 37 | 2024年 10月30日(水) |
矢ヶ部 晃(データサイエンス学科2年)
|
武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024 | paizaトロフィー賞 | 武蔵野大学×paizaランクチャレンジ2024表彰式 |
| No. | 発表日 | 教員/学生 | タイトル | 発表タイトル | 掲載メディア/登壇イベント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023年 9月15日(金) |
廣瀬 侃大 (数理工学科3年) | スーパーで商品の場所を多言語で案内するpepper | Pepper's Rescue賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 2 | 2023年 9月15日(金) |
安達 美月 (人間科学科3年) | いつでも気軽にストレスを確認できるPepper | 感動賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 3 | 2023年 9月15日(金) |
鴻野 駆流 (政治学科3年) | App Storeのレビュー情報分析に基づく価値観に応じたゲーム推薦サービス | ベストバリュークリエーション賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 4 | 2023年 9月15日(金) |
進藤 匠 (教育学科3年) | 児童の学びに効果的な教師の発問とは ~教師の授業力向上に向けたリフレクション~ | NTTデータ・イントラマート賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 5 | 2023年 9月15日(金) |
江口 奈穂・倉次 野恵 (教育学科3年) | 対話型生成AIを解答者とする作問学習による生徒の知識の活用力向上の試み | ワークアカデミー賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 6 | 2023年 9月15日(金) |
薛 子慧 (アントレプレナ―シップ学科3年) | ChatGPTを使ったワンオペ事業運営ガイド | AIreadyUniv賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 7 | 2023年 9月15日(金) |
村井田 琉菜 (法律学科3年) | ユーザの属性や価値観を反映した口コミデータのフィルタリングによる情報推薦方式 | 実験の実現性の高さと視点の切り口を称える賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 8 | 2023年 9月15日(金) |
長谷川 大和 (経営学科3年) | ヒット曲の歌詞データの感情分析による年別感情推移の可視化方式および感情と出来事の関係性の調査 | 情報×情報からの情報の産み出しに価値をつけたで賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 9 | 2023年 9月15日(金) |
金澤 航史 (環境システム学科3年) | 口コミによる江東区観光地の分析 | サステナブルな地域づくり貢献賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 10 | 2023年 9月15日(金) |
東郷 龍誠・村上 萌々子 (経済学科3年) | oViceのUIにおける課題と改善案 | 経済学科賞(AI) | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 11 | 2023年 9月15日(金) |
藤田 萌花 (法律学科3年) | 歌詞の感情推移分析による類似楽曲の推薦方式 | 法律学科賞 | 副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 12 | 2023年 9月15日(金) |
星川 真菜 (環境システム学科3年) | 友好的会話と信頼構築を利用したPepperによる夜道の恐怖緩和 | AI副専攻 優秀賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 13 | 2023年 9月15日(金) |
勝山 隼斗 (経済学科3年) | 新しい学習環境「響室」の評価手法の検討 | AI副専攻 優秀賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 14 | 2023年 9月15日(金) |
齊藤 理那 (社会福祉学科3年) | 人の役に立ちたいと考えている方必見!闘病ブログのかきかた~情報が得られるブログ、タイトルとブログの文字数に関係がある!?~ | AI副専攻 優秀賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 15 | 2023年 9月15日(金) |
渡辺 杏奈 (環境システム学科3年) | サイバーキャンパスを使ったAR情報アプリin 屋上菜園 | AI副専攻 優秀賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 16 | 2023年 9月15日(金) |
新川 大海 (日本語コミュニケーション学科3年) | 擬似人格対話AIサービス「Operlogue–オペラローグ-」 | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 17 | 2023年 9月15日(金) |
白波瀬 拓 (経済学科3年) | レビューをもとにあなたに合ったゲームを探そう!ゲーム×アキネーター=ゲーネーター | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 18 | 2023年 9月15日(金) |
布施 諒一 (法律学科3年) | 対話型生成AIを活用したTOEIC試験対策の一手法 | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 19 | 2023年 9月15日(金) |
石田 桃香 (人間科学科3年) | ぴーなっつ最中の販促方法の提案 | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 20 | 2023年 9月15日(金) |
佐藤 理奈 (日本文学文化学科3年) | ユースキンの特徴をより伝えるための提案~口コミ分析と公式HPの情報から~ | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 21 | 2023年 9月15日(金) |
清水 悠希 (経営学科3年) | セールスランキングとファンアート作品数から見るソーシャルゲームの人気を構成する要素 | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
| 22 | 2023年 9月15日(金) |
永島 和馬 (経済学科3年) | アニメキャラクターにおける人気要素とギャップの分析 | AI副専攻 奨励賞 |
副専攻(AI活用エキスパートコース)成果発表会・修了式 |
紀要
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第6号
〔2024(令和7)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言 : 「特集:武蔵野大学における情報教育の現在地」について | 林 浩一 | P3 |
| 情報科目における多様な学生の学修意欲の向上に向けた受講順序の入替と最終課題の調整の試み | 中村 太戯留 | P4-11 |
| メディアリテラシー[表現力]の実践報告 | 斉藤 憲仁 | P12-22 |
| オンデマンド授業動画の視聴と学生の感情状態との関係 | 宮田 真宏 | P23-32 |
| 大学における競争型プログラミング教育の実践 : paizaランクチャレンジを通じた武蔵野大学の事例 | 渡邊 紀文、糸田 孝太 | P33-45 |
| ゲームエンジンを利用した3D可視化手法の教育の実践例 | 圓崎 祐貴 | P46-57 |
| グループワーク貢献度の学生の自己認識に関する検討 | 田丸 恵理子、宮田 真宏 | P58-70 |
| 演習を含む授業におけるグループワーク時間の確保のための科目連携およびタイムシェアリングの試み | 中村 太戯留、岡田 龍太郎 | P71-78 |
| 大規模言語モデル(LLM)を用いたチャットボット構築の情報科目授業での実践と考察 | 糸田 孝太、渡邊 紀文、岡田 真穂 | P79-93 |
| 課題解決型授業における生成AIの活用について | 中山 義人 | P94-112 |
| 「人工知能実践プロジェクト」授業実践報告 : 学生の興味関心を起点としたテキスト分析とARアプリ開発 | 武藤 ゆみ子、圓崎 祐貴 | P113-123 |
| 武蔵野大学におけるAI副専攻と主専攻との連携を目指した学生のプロジェクトテーマへの学科関心の取り込み事例 | 林 浩一 | P124-134 |
| 複数視点映像を用いた顧客行動の分析手法の提案 | 木口 春花、田丸 恵理子、宮田 真宏 | P135-149 |
| サステナビリティの浸透性と購買行動との関係 : 文房具店の取り組みに着目した分析 | 林 利咲、宮田 真宏 | P150-161 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第5号
〔2024(令和6)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言 : 「ミニ特集 : 副専攻AI活用エキスパートコース完結」について | 林 浩一 | P3-4 |
| サービスデザインのアプローチを取り入れた武蔵野大学AI副専攻コースのコンセプトと実践 | 林 浩一 | P5-32 |
| 予測力の育成に向けた「データサイエンス活用」の取組 | 中村 太戯留、岡田 龍太郎 | P33-40 |
| プロトタイプのブラッシュアップサイクルを重視したサービスデザイン授業の学修効果 | 田丸 恵理子 | P41-53 |
| ロボットを活用した課題解決型授業の設計とその実践 | 渡邊 紀文、宮田 真宏 | P54-68 |
| 人工知能実践プロジェクトの「AIツールを用いたトレンド分析・サービス提案」というテーマについて | 朝倉 大樹 | P69-80 |
| 響学スパイラル評価のための会話場面に注目した教室環境分析の試み | 勝山 隼斗、進藤 匠、田丸 恵理子、宮田 真宏 | P81-90 |
| レビュー分析によるヒットするゲーム要素の抽出および評価手法の検討 | 白川 桃子、渡邊 紀文、宮田 真宏 | P91-100 |
| マルチターンで学生の問いを解決するプログラミング学習支援チャットボットの試作 | 上地 泰彰、田丸 恵理子、渡邊 紀文 | P101-119 |
| 非認知能力の育成に向けた「メディアリテラシー」の取組 | 中村 太戯留、寺田 倫子、鈴木 大助、中山 義人 | P120-127 |
| その学問領域とは別の分野を専門として持つ受講者がメイン層である講義を行う際に講義者として心がけていること | 朝倉 大樹 | P128-141 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第4号
〔2023(令和5)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言 : 「ミニ特集 : スマートインテリジェンス学習環境のデザイン」について | 上林 憲行 | P3-4 |
| 響学スパイラルを具現化する教育学習環境イノベーション : 響室・響場ビジョンとその意義 | 上林 憲行 | P5-11 |
| 教室をリ・デザインする | 風袋 宏幸 | P12-24 |
| 響き合う学びを支える学習環境の構築と実証実験 | 田丸 恵理子、大﨑 理乃 | P25-36 |
| 顔情報を用いた教室空間センシングの取り組みと今後の展望 | 宮田 真宏 | P37-46 |
| 大教室での複数並列グループワークにおける,音声取得とテキスト変換精度の有効性の実証 | 小笠原 豊、大橋 一広 | P47-53 |
| 反転授業の導入を容易にする反転型反転授業パターン | 林 浩一 | P54-64 |
| 情報科目におけるBYODを利用した情報活用スキルの育成 | 中村 太戯留 | P65-72 |
| コラボレーションツールを利用した学生の個別サポートにおける情報共有環境の構築 | 渡邊 紀文、上地 泰彰、田丸 恵理子、圓崎 祐貴、岡田 龍太郎、糸田 孝太、岡田 真穂、守谷 元一、宮田 真宏 | P73-82 |
| 協調的創造活動を取り入れた混合型オンライン授業の実践 | 大﨑 理乃 | P83-91 |
| 副専攻AI活用エキスパートコースのコミュニケーション施策 | 横山 誠 | P92-104 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第3号
〔2022(令和4)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言 : 特集 副専攻 (AI活用エキスパートコース) の立ち上げ | 上林 憲行 | P3 |
| AI活用エキスパート副専攻コースの構想 | 上林 憲行 | P4-14 |
| 武蔵野大学響学スパイラルに基づく授業設計と評価手法 : 情報技法基礎の授業での実践 | 林 浩一 | P15-30 |
| 情報技法発展Aにおけるオンライン授業の実践と課題 | 宮田 真宏 | P31-42 |
| 授業やオープンキャンパスでの学生のプレゼンテーションのオンライン化についての取り組みと考察 | 圓崎 祐貴 | P43-51 |
| オンデマンドコンテンツと同時双方向型授業を組み合わせたプログラミング教育の実践 | 岡田 龍太郎 | P52-60 |
| 同時双方向型オンライン授業におけるアイスブレイクの検討と実践 | 大﨑 理乃 | P61-68 |
| フィードバックを重視したサブ講師の担任制と情報必修科目での実践 | 中村 太戯留 | P69-77 |
| プログラミング科目でのオンラインでの個別指導と情報共有環境の構築 | 渡邊 紀文, 横山 誠, 圓崎 祐貴, 岡田 龍太郎, 宮田 真宏 | P78-86 |
| 副専攻AI活用エキスパートコースの広報 | 横山 誠 | P87-95 |
| ヘルプデスク運用データの比較に基づくICT活用授業サポートの効果の分析 | 田丸 恵理子 | P96-108 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第2号
〔2021(令和3)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言 : オンライン授業実践と全学支援特集について | 上林 憲行 | P3 |
| コロナ禍における緊急避難的代替措置としての全学オンライン授業支援の戦略と戦術 : その記録,レビュー,インパクトについて | 上林 憲行 | P4-21 |
| 情報必修科目における対話的なオンライン授業の試行 | 中村 太戯留 | P22-29 |
| 情報科目におけるオンライン授業の実践と課題 | 斉藤 憲仁 | P30-47 |
| 論証図を用いた反復演習による学生の論理思考スキル改善 | 林 浩一 | P48-59 |
| 問題解決を重視したプログラミング教育とオンラインでの実践 | 渡邊 紀文 | P60-67 |
| プログラミング科目におけるオンライン演習室の取り組みと考察 | 岡田 真穂 | P68-76 |
| 演習形式授業のオンライン化についての考察と取り組み | 圓崎 祐貴 | P77-82 |
| 授業のオンライン化に際しての教員支援の試み | 藤本 かおる | P83-93 |
| 大学でのインフォーマルなオンライン交流会の試み :「夜ふかしRemo会」の開催 | 岡田 龍太郎 | P94-103 |
| ヘルプデスクの一年間の運用経験に基づくオンライン授業を支えるユーザサポートの検討 | 田丸 恵理子 | P104-119 |
| 武蔵野大学ポータルサイト「MUSCAT」の現状調査 | 横山 誠 | P120-132 |
Musashino University Smart Intelligence Center 紀要 第1号
〔2020(令和2)年3月発行〕
| タイトル | 著者 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 巻頭言:MUSICの紀要の発刊に寄せて | 上林 憲行 | P3 |
| 図解要約を活用した表出型の授業実践 | 中村 太戯留 | P4-7 |
| クラウドベースのコンピュータ基礎教育とツールを活用したグループ活動の実践 | 渡邊 紀文 | P8-14 |
| 情報基礎科目としてのデザイン思考授業の試行と評価 | 田丸 恵理子, 上林 憲行 | P15-24 |
| 新入学生の情報リテラシーに関する実態調査 | 田丸 恵理子 | P25-37 |
| 活動報告1:2020年度カリキュラムデザイン | P38-52 | |
| 活動報告2:入学前学習 | P53-54 | |
| 活動報告3:BYODキャンパス化 | P55-61 | |
| 活動報告4:教育・学生支援サービス開発 | P62-67 | |
| 活動報告5:各種委員会活動 | P68-73 |

