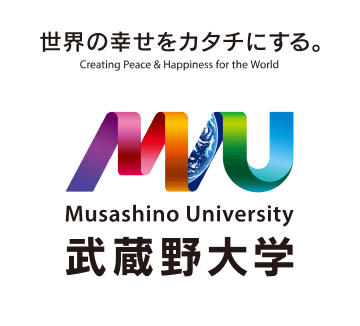第3回 刑法学 法学部 法律学科 林 弘正 教授(取材当時)
新たな社会的課題へのアプローチを通して、刑法学の領域を拡大

法学部法律学科 教授(取材当時)
中央大学法学部法律学科卒業。中央大学大学院法学研究科刑事法専攻修士課程修了。 同 博士課程単位取得退学。アライアント国際大学カリフォルニア臨床心理学大学院臨床心理学研究科修士課程修了。島根大学大学院法務研究科教授などを経て、2014(平成26)年より現職。島根大学名誉教授。
刑法学というと、数ある法律分野の中でも、犯罪と刑罰という厳格な分野を扱うがゆえの、非常に気難しい雰囲気を感じます。 そこで今回は、知的探究心をもとに現代的課題への柔軟なアプローチを続け、刑法学のすそ野を広げている、法学部の林弘正教授の研究をご紹介します。
先行研究のない分野を、ゼロから切り拓く
非日常を扱う「刑法」
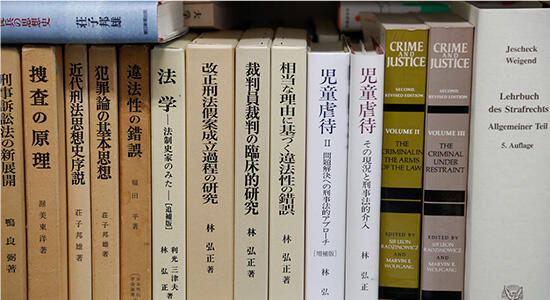
「刑法」という言葉そのものは、新聞やニュースなどで、みなさんも日常的に目や耳にされていると思います。 いわゆる六法といわれるものは、「憲法」「民法」「刑法」「商法」「民事訴訟法」「刑事訴訟法」から成っています。ここから、国家のかたちを規定する憲法、裁判の仕組みを定める民事訴訟法及び刑事訴訟法を除いた、民法・刑法・商法が、その社会の基礎となる法律であるといえます。 ごく簡単に言えば、その社会において、民法は人と人との関係におけるルール、刑法は何が犯罪となるのかとそれを犯した場合の刑罰のルール、商法は会社のあり方や商取引のルールであると考えていただければよいでしょう。 個人の方でも、家屋の購入や相続などの際には民法に、仕事を通じて商法に触れる機会はあると思います。しかしながら、刑法については、犯罪と刑罰を扱うという性格上、日常のくらしとは縁遠い(また、そうあって欲しいと願う)、非日常を扱う法律であるといえるでしょう。
学際的な問題に、刑法の視点から

このため、「刑法学者」が普段どんな研究をしているかということも、法学部で学ばれた方以外はなかなかイメージが湧かないかもしれません。 他の学問分野と同じように、ひとえに「刑法学者」といっても、その研究テーマは百人百様です。法理論や体系、個々の犯罪や刑罰の事例研究、時代の変化を先取りした新たな問題の提起、外国との比較、法制史など、様々な分野や切り口があります。 その中で、私は比較的ユニークな研究対象を取り上げてきたと思います。大学院や若手研究者時代こそ、「違法性の意識」といった犯罪論の大きなテーマや外国の判例研究に取り組みました。しかしその後は、法制史研究を挟みつつ、児童虐待や裁判員裁判制度、先端医療といった現代的かつ学際的な問題に、刑法の視点からアプローチしてきました。 ちなみに、重大な刑事事件の裁判に国民が参加する裁判員裁判制度、これを異分野と言うと意外に思われるかもしれません。しかし、主として刑事裁判の手続論・方法論の研究になりますので、刑事訴訟法研究者の専門領域になるのです。
研究を深める中で、異分野の修士号を取得

児童虐待(Child Abuse)についての研究は、1991年から継続的に取り組んでいます。当時は、刑法学者によるこの分野の研究はほぼゼロで、今でもそれほど多くはありません。 しかし、それがゆえに、児童福祉や精神医学など他分野の専門家が、私の論文や著作を読み、引用してくれるということが起こりました。私自身も、そういった多方面の研究者との交流から、刑法学者としての研究の視座と視野が大きく広がりました。 さらには、被害者の方との対話を通して、法的な相談以外の面でも有用な対応ができればという思いを抱き、米国の大学の日本校で臨床心理学の修士号を取得するに至りました。 修士号の取得には400時間のプラクティカム(臨床実習)が必修で、クライアントと向かい合いました。50代半ばになって、若いクラスメイトと席を並べてディスカッションし、4年間をかけて学んだ経験は、本当に貴重なものでした。
「10年経って評価される」研究を

また、それら現代的課題と並行して進めている法制史研究も、昭和2年から開始された刑法改正事業の経緯を考察し、昭和15年に成案となった「改正刑法假案」を対象としたもので、こちらも先行研究がほとんど存在しない分野でした。 「改正刑法假案」は、明治15年旧刑法に続いて現行刑法が成立して以来、刑法改正が試みられた中での一つの集大成となる刑法改正案です。この成立過程を丁寧に読み解いていくことで、時代によって個々の犯罪の概念や類型がどう変化していったのかを明らかにすることができるのです。 このテーマは、恩師であり、律令を中心とした日本法制史研究の第一人者である利光三津夫先生が勧めてくださったものでした。先生は常々「書いた論文が、10年経って評価されたら本物だ」とおっしゃっていました。 その後、地道に論文を書き続け、2003年に1冊の論文集にまとめ、5年ほど経った頃でした。学会で、次世代をリードする新進気鋭の研究者に声をかけられ、「先生の假案のご研究に注目しており論文集には全て目を通しています。假案の論文集は、ゼミで学生に読ませています。」という話を聞かされました。 利光先生の教えの素晴らしさを改めて感じるとともに、研究者冥利に尽きる出来事でした。
研究者としてのあゆみ
タテではなく、ヨコの世界を目指して

私の場合、他の先生方のように、子どもの頃から研究者を志していたわけではありません。もとを辿れば、親の影響というものは確かにありましたが、親と違う道に進みたいという少々ネガティブな理由と社会に貢献したいとの願いがありました。 私の父はサラリーマンだったのですが、常にタテのプレッシャーにさらされて、苦労をしているようでした。そこで、弁護士など法律の世界であれば、企業のタテ社会に比べればだいぶフラットであろうと考えて、中央大学の法学部に進学したのです。 しかし、学部の2年次に自主ゼミと出会ったことで、司法試験受験という道から、研究者の道にシフトすることになります。博士課程の先輩が、学部生10名くらいを指導してくれるのですが、ここでの学びが楽しく、留年して6年も在籍しました。 当時は授業料が年間3万円と格安だったからできたことです。講義には出席するものの、卒業要件を満たさないよう「単位を付けないでください」と先生に頭を下げる、変わった学生でした。
42歳で専任教員に

その後、修士課程、博士課程を経て、大学で専任ポストを得たのは42歳になってからです。当時は、学部修了後にすぐに助手になるケースもありましたから、研究者としてはかなり遅咲きです。 ただ、自主ゼミ終了後もマンツーマンで指導してくださった研究者の先輩から、ストレートに専任教員になるパターンではない場合、いわば「苦節10年の道」の心構えというものを教え込まれていましたので、挫折せずに乗り切ることができました。それは、「自分の能力に自信を持つこと」、「経済的基盤を確立すること」の2つです。大学の非常勤講師として研究と教育に携わることで前者の、個人で塾を運営することで後者の課題を乗り越えることができました。 また、研究に傾注しつつも、他に楽しみを持っていたことも、苦しい時代をうまく乗り切れた理由だと思っています。陶芸、染織、漆芸などの美術の世界、寺社仏閣、お茶、日本酒など、様々なことに興味を持ち、専任教員になって研究と教育、学事に追われるようになってからも、続けています。
今後の展望
研究成果を教育にフィードバック

今年度いっぱいで定年を迎えますが、今の研究テーマを追い続けるとともに、その成果をきちんと教育にフィードバックし続けていきたいと考えています。 これまでは、ある程度の年齢になると、新たな論文を書くことなく、教育にシフトするようなスタイルもまま見られました。しかし、私は継続的に新しいテーマに取り組み、得た知見や刺激を自分の学生に還元していくということに、愚直に取り組んできたつもりです。 例えば、裁判員裁判に関しては、学生全員に傍聴とレポートを課しました。それにより、単に法律的な学びを深めるだけではなく、いつ裁判員に選任されるかわからないという実感や法律を学んだ者としての心構えを持ってもらうことができました。 これからも、従来の研究テーマや、この7年来研究している先端医療と刑事法の交錯領域についての研究を続けつつ、教育にも還元していきたいと思います。
読者へのメッセージ

私は、研究者人生において、研究のニーズや必要性といったことではなく、あくまで「自分の問題意識」を追い続け、そこで見出した課題を世に問うということを繰り返してきました。 そうすると、分野横断で知見が広がり、ネットワークができ、そこから次の「問題意識」が生まれてきます。 そうして現実に生起する社会の課題に向き合い、研究を進めれば進めるほど、多くの矛盾に直面し、ただ一つの正解などないということを実感させられます。 しかしながら、そこで矛盾を自覚しつつ、一方で考えることをやめないことが、研究者だけではなく、社会を生きる私たちに必要なことではないかと考えます。 世の多くの人に、「自分の問題意識」に向き合い続けることの価値を認識していただけたら幸いです。