
第55回 公衆衛生学 教育学部 幼児教育学科 峰 友紗 准教授
幼児期の健康に公衆衛生の視点からアプローチ
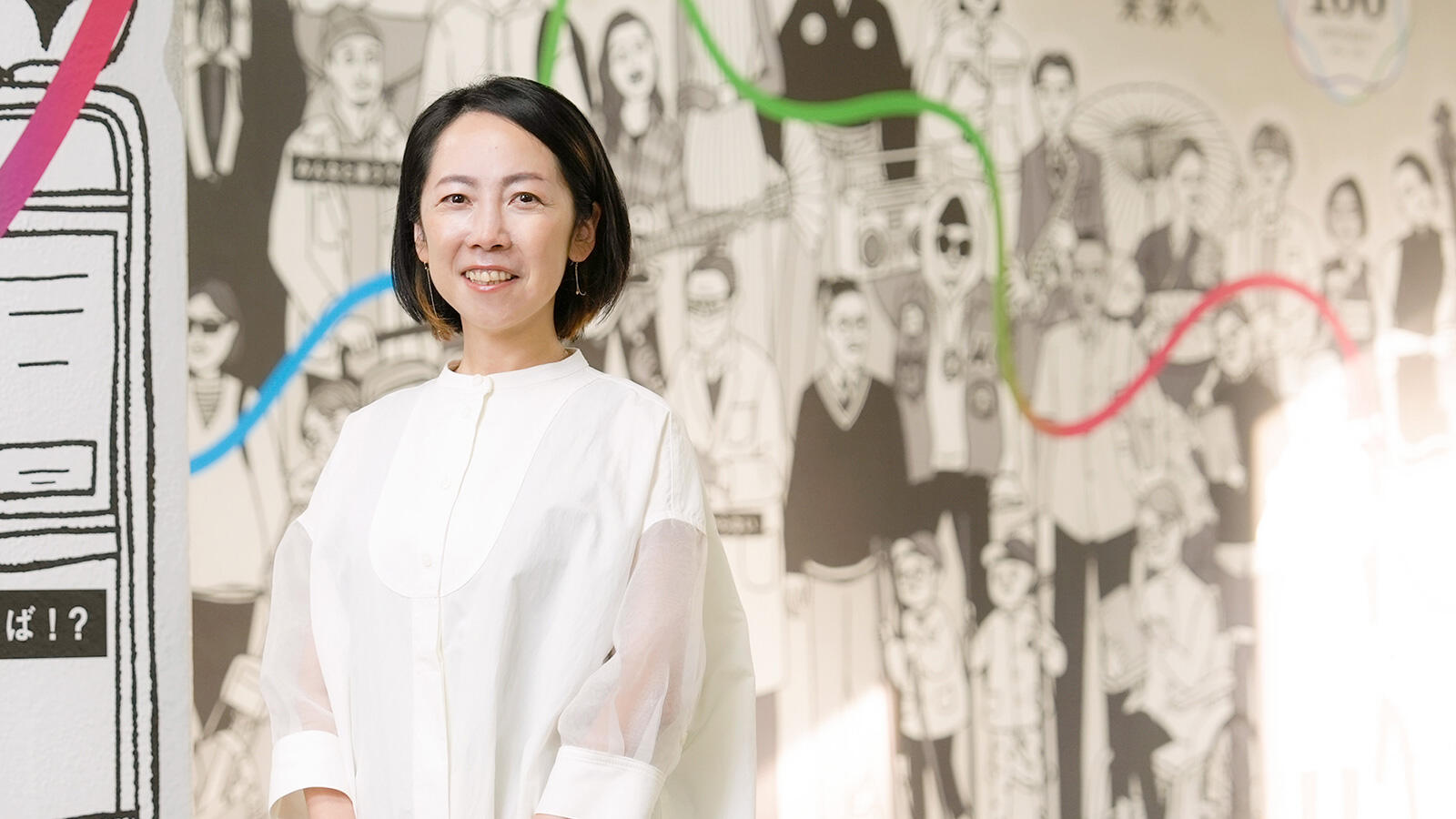
教育学部 幼児教育学科 准教授
東京慈恵会医科大学医学部看護学科卒業。東邦大学大学院医学研究科博士課程修了。博士(医学)。大学で看護師・保健師資格を取得。国立公衆衛生院専門課程を修了後、東京都大田区の保健師として9年間勤務。その後、看護基礎教育に携わり、東京慈恵会医科大学医学部看護学科助教、尚絅学院大学総合人間科学系准教授を経て、2022年より現職。専門は公衆衛生学、母子保健学。
乳幼児期の子どもの健康は、学童期、成人期にいたるまで生涯の健康の基盤になることが知られています。乳幼児の健康づくりには、家族はもちろん、保育所や幼稚園において子どもたちと関わる保育者の役割もとても重要です。保健師としての現場経験を持ち、母子保健を専門とする峰准教授は、乳幼児期の健康に対して公衆衛生の視点から、保育・幼児教育のフィールドにアプローチし、親子の幸せにつながる教育と研究に力を注いでいます。
研究の背景
母子保健から幼児教育のフィールドへ

大学の看護学部を卒業後、地域の親子のために仕事がしたいと考え、公衆衛生、母子保健の実践や研究の道に進みました。行政の保健師として働く中で、特に周産期の母子の健康に興味を持つようになり、大学に戻って研究や看護基礎教育に力を注ぎ、7年前から保育・幼児教育のフィールドで教育と研究を行っています。
我が国において、子どもの公衆衛生や予防医学に関する研究は、周産期~3歳ごろまでの研究が中心となっている「母子保健」、小学校入学後を対象とした「学校保健」の領域での研究が中心で、その2つに挟まれた幼児期に関する研究は、圧倒的に少ないのが現状です。一方で、幼児期の健康は、生涯にわたる健康に影響を及ぼすと言われており、国際的にも幼児期の健康づくりが注目されてきています。この時期の子どもの健康にまつわる教育と研究に取り組み、なかでも特に、幼児期の身体活動にスポットを当てた研究を進めています。
研究について
幼児の身体活動量を評価する質問票を作成
-座位時間の長さが将来の健康リスクに-

近年、座位時間が長いと死亡リスクを高めるという研究結果が示され、じっとしている時間をいかに減らすかが健康づくりのカギを握ることが分かってきました。特に子どもにおいては、身体活動量(お手伝いや通園・通学など生活活動や運動)、座位時間(テレビやスクリーンメディアを使うなどのじっとしている時間)、睡眠時間のバランスが重要であり、WHOもその指針を出しています。座位時間や身体活動量は、子どものころの習慣が大人に移行しやすく、大人になってから運動しようとしたり、じっとしている時間を減らそうとしても、なかなかうまくいかないと言われています。つまり、生涯にわたる健康づくりのためには、幼児期や学童期の行動や生活がとても重要になってきます。
一方、スマートフォンやタブレット端末の普及やコロナ禍による社会の変化によって、今、子どもたちの身体活動量の減少と座位時間の増加が指摘されています。効果的な対策を講じるためには、現状を客観的に把握する必要があるのですが、日本を初め世界的にも幼児期の身体活動量を評価できる手法が少なく、それが難しい状況にあります。幼児の場合、身体活動量を測るデバイスなどを身に着けても正確な計測ができない可能性やかえって活動が制限されることがあることから、子どもの身近にいる大人が質問票に答える形で把握しようと考え、その質問票を作成する研究に取り組んでいます。
-日本の生活文化にあった内容を検討-
今回作成している質問票は、海外で開発された質問票の「日本版」に当たるもので、質問項目は、遊びや運動で活動した時間、どの程度の強度の活動だったか、テレビやスマホなどスクリーンメディアを見ていた時間、睡眠時間など多岐にわたります。
すでにある質問票を使うとはいえ、海外と日本では生活、文化、子どもを取り巻く生活環境が異なります。そのため、単に日本語に翻訳するだけでなく、日本に合った質問や選択肢にする必要があり、検討を進めているところです。また、幼児期の子どもたちの多くは、平日の日中は幼稚園や保育園、朝夕と休日は家庭で過ごし、平日と休日で睡眠時間や生活スタイルも異なります。そのため、保護者だけでなく幼稚園教諭や保育士も回答者とし、休日を含む数日間の様子を答えてもらうことを想定しています。
日本版をまとめた後、英語に再翻訳して海外版と項目や内容に齟齬がないかをチェックし、国際比較に使えるものに仕上げていく予定です。作成した質問票は、幼児の身体活動量の一つの指標として、家庭と保育施設の両方で活用できるものにしたいと考えています。
妊娠中のたばこと子どもの肥満リスク
また、これまでに取り組んできた研究テーマとして、妊娠中の母親の喫煙と出生後の子どもの肥満リスクや、低出生体重児に関する疫学研究があります。

日本では、約1割の子どもが低出生体重(2,500g未満)で生まれており、先進国のなかでもかなり高い割合で推移しています。低出生体重の原因のひとつとして、母親の喫煙などの生活習慣の影響が指摘され、その後の肥満や大人になってから生活習慣病になりやすいこと等も分かっています。そこで、肥満や生活習慣病発症のリスク要因といわれる乳幼児期の急激な体重増加に着目し、妊娠中の喫煙と急激な体重増加の関連を明らかにしました。
低出生体重になる原因の中で、日本で特に問題視されているのが、若い女性のやせ(BMI18.5以下)の影響です。日本は成人女性のやせの割合が高く、妊娠前からのやせは低出生体重のリスクに影響を与えます。こうした母子保健に関する知識は、一見、幼児教育と直接結びつくものではありませんが、折に触れて若い学生のみなさんに伝え、日々の食事や生活を見直すきっかけにしてもらえたらと思っています。
今後の展望
健康を「みんなでつくりあげるもの」に

健康づくりの国際的な理念に「ヘルスプロモーション」という考え方があります。ヘルスプロモーションとは、「人々が自らの健康をコントロールし、改善できるようにするプロセス」と定義されており、健康とは目的ではなく「その人らしい人生や幸せな生活」への手段であること、そして、健康づくりは医療やヘルスケアに関わる人だけでなく、あらゆる人が取り組むものであるという概念です。
私たちはよく「健康のため」という言葉を使いますが、本当は「健康になること」がゴールではありません。健康になることは、あくまでも自分らしく生活することや自分のやりたいことを実現するための手段です。私の研究も、単純に「幼児期の身体活動量が少ないと健康に良くない」と結論づけることがゴールではありません。研究を通して、子どもが健やかに育つための方策を考え、保護者や子どもに携わる人と共有し、子どもたちや人々の生活がより楽しく幸せになることに少しでも貢献できたらと考えています。
また、健康づくりや予防医学は“医療の問題”としてイメージされることが多いのですが、そんなことはありません。たとえば、まちづくりの視点から歩きやすい道を作る、子どもの体をつくる栄養バランスの良い給食を考えるために教育と連携するなど、健康は、社会のあらゆる分野の人が関わり、みんなでつくり上げていくものなのです。自分の専門である母子保健学や公衆衛生学と、幼児教育、保育の分野のコラボレーションを進め、子どもたちが健康で幸せに生活するために何ができるかを具体的に考えていきたいと思っています。
教育
身に付けてほしい「広い視野」と「直感をうけとるセンス」

子どもの保健、子どもの健康と安全、病児保育論など、子どもの健康に関する授業を担当しています。授業を通して、学生のみなさんには、特に2つの力を養ってほしいと考えています。
まず1つ目は、個から社会、社会から個に目を向ける相互的で広い視野です。子どもや親子を取り巻く環境は、多様化、複雑化が進んでいます。たとえば、子どもの夕食や就寝の時間が遅くなる背景には、保護者個人では解決できないような、短時間勤務に対する企業や同僚の理解不足など社会的な要因もあります。子どもや親個人へのアプローチも大切ですが、それと同時に、どのような社会になれば親子を取り巻く環境がよりよいものになるのか、多角的に考える視点をもってほしいと思っています。
もう1つは、自分の五感や気付き、感覚を大切にする意識です。私が担当している授業は、子どもの健康や安全を守る専門的な知識と技術が学びの多くを占めています。子どもに関わる仕事に就く上で、その知識や技術は不可欠なものですが、それと同じくらい、知識と技術を生かすためには、まずは感覚器官で事態を捉え、気付く力が重要だと考えています。幼児教育学科には、五感を養い、感覚を研ぎ澄ませる授業がたくさんあります。学科全体の学びを通して気付く力を磨き、さまざまな感覚と専門知識・技術を連動させながら、子どもたちの成長を支える人材になってほしいと思っています。
どのフィールドでも“親子の幸せ”のために
大学に入った時は、なんとなく小児科の看護師になりたいなと思っていました。でも在学中に方向転換をして、公衆衛生の研究をしたり、保健師として働いたり、看護学科の教員になったり、いろいろな経験をして今に至ります。

私は大学という場が好きで、学びたいという思いを誰にも邪魔されない、とても贅沢な空間だと思っています。教員をしているのも、教えることが好きというより、学生と対等な立場で学び合って楽しませてもらっているという感覚です。私のゼミでは、公衆衛生が専門の私と、保育や幼児教育を学んできた学生たちとで、どんなコラボができるかを探っていくのも面白いなと感じているところです。
看護や医学からどうして幼児教育に?とよく聞かれます。たしかに、職場としての学問のフィールドは転々としてはいるのですが、私としては「どんなフィールドにいても、自分の研究や取り組みの先に“親子の幸せ”があればそれでいい」というスタンスでいるので、そこはブレていないなと思います。親子の幸せへの関わり方にはいろいろな形があり、「自分が今いる場所」にあまりこだわらずにフットワーク軽くやっていきたいです。
好きなように自由に文字を書く

今、文字を書くことが楽しいですね。小さい頃に書道をやったり、大人になってからもカリグラフィーをやっていて、もともと字を書くことは好きだったのですが、ここ数年は、好きな道具で好きな文字を好きなように書くというちょっと変わったお稽古に通っています。いわゆるきれいで読みやすい文字にはこだわらず、その時に使いたいペンやニブ(ペン先)、インクで好きなように文字を書く。ただそれだけなのですが、とても楽しい。これまで、字を書くことすらいろんなルールにとらわれてきたんだなと気付くきっかけにもなりました。書いた文字でオリジナルの切手とはがきを作って年賀状にしたり、ステッカーを作ったりして、こっそり楽しんでいます。
読者へのメッセージ

コロナ禍を経て、「健康」はこれまで以上に注目されるようになりましたが、健康は人々の生活を豊かにするためのひとつの手段に過ぎないということを改めて感じています。公衆衛生学は、その地域で生活する人々のこころと身体、取り巻く環境を包括的に捉えることで、コミュニティとそこで生活する人々の幸せやウェルビーイングを考え、実践につなげる学問です。
健康は、個人がストイックに追求するものではなく、常にどこかで穏やかさと緩やかさを感じられる社会の中で育むことができたらと思います。医療関係者だけでなく、あらゆる分野の専門家、多くの企業や地域コミュニティ、そして市民とのコラボレーションのなかで多様な視点を持ち寄ることで、誰もが健やかに暮らせる社会を築いていけたらと考えています。
取材日:2025年1月

