
第56回 教育工学 教育学部 教育学科 中村 駿 准教授
教師の知を探る
優れた“わざ”を共有可能なものに
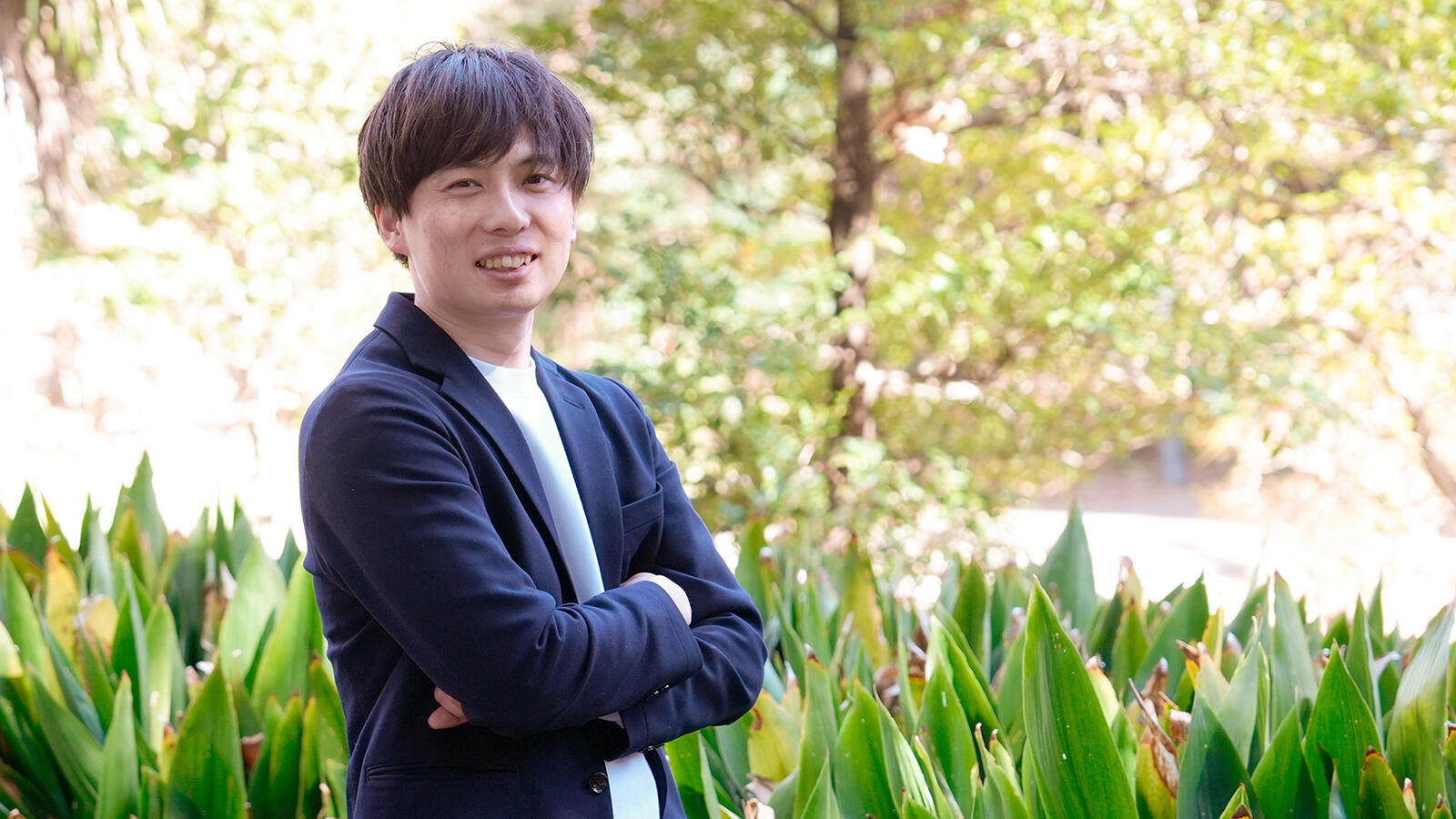
教育学部 教育学科 准教授
早稲田大学人間科学部卒業。早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程修了。博士(人間科学)。早稲田大学人間科学学術院助手、立教大学大学教育開発・支援センター助教を経て、2021年4月より現職。専門は教育工学、授業研究、教師研究。
教師は、学校教育においてとても重要な役割を担う存在です。授業や日常生活の中で子どもたちが見せるちょっとした成長の芽を見つけ、その芽を伸ばしていくため、教師はさまざまな“わざ”を駆使しています。教師がそうしたわざをいかにして身に付けることができるのか、教師の学びと成長をテーマに研究を行っているのが中村准教授です。教師の認知や思考を分析し、優れた教師の知を伝承可能なものにすることを目指す中村准教授の研究を紹介します。
研究の背景
教師の成長や授業力量向上につながる研究
私の専門である教育工学は、教育学、心理学、情報科学などさまざまな学問分野を融合させて教育の現象を捉え、問題解決を図る学問です。その中でも私は、教師という人間に着目し、優れた教師が持つ専門性とは何かを解明するため、学生時代から研究を進めてきました。
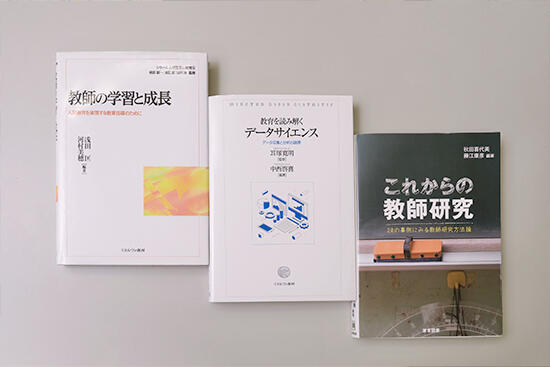
教師の優れた授業は“わざ”といった言葉で表現されますが、多くが感覚的なもので、ほかの教師に伝えにくいという課題があります。経験やコツを多くの教師に共有し、成長に繋げるためには、わざの奥にある素晴らしい知の正体を解き明かすことが必要です。そこで私は現在、授業における教師の認知と成長、ICT活用における教師の思考という2つのテーマを柱として研究に取り組んでいます
研究について
授業における教師の視点や意味付けを分析
-優れた教師は何を見ているのか-
教師の成長にとって、経験を積むことはもちろん大事ですが、それだけで成長できるとは限りません。授業を重ねる中で、自らどんどん改善していくことができる教師もいれば、そうではない教師もいます。その違いを生む要素として、私は授業中の教師の「認知」に着目し、教師が授業中に注目しているところやその意味付けの仕方の分析を進めてきました。
これまでの研究では、授業中に若手教師は子どもの姿勢をよく見ている一方、ベテランの優れた教師は、姿勢はもちろん、それ以上に顔をよく見ていることが分かっています。子どもの感情や興味は表情によく表れるため、ベテラン教師は顔を見て子どもが関心を持っているか、授業がうまく進んでいるかを認知し、その情報を授業展開や今後の授業改善に役立てていました。また、ベテラン教師はある一時点の出来事といった「点」だけでなく、点と点を結び、授業の流れという「線」も見ていることが分かりました。授業中にどこに注目するか、見たものを線にして意味づけられるかという2つの点で、若手とベテランには違いがあることが、研究を通じて見えてきたのです。
さらに、優れた教師は授業の流れを予測し、その予測と子どもの反応を照らし合わせながら授業を進めていることも分かりました。予測を立てることで、予測と違う反応があれば、それを学びにすることができます。たとえば「ここはじっくり考える時間になるだろう」と予測していた場面で、子どもたちから簡単に手が挙がれば、「自分の問いかけ方が良くなかったのかもしれない」と気付き、改善に繋げられるというわけです。
研究を通じて、授業中に教師が想像以上にさまざまなことを認知し、考えていることが明らかになり、あらためて教師の素晴らしさ、教師を研究する面白さを実感しているところです。
-360度カメラやVRゴーグルも研究に利用-

さらに現在、360度カメラで撮影した授業の映像をVRゴーグルで教師や学生に視聴してもらい、どのように授業中の状況を把握し、判断しているのかを分析しています。見ている映像は同じでも、学生と優れた教師では視点や受け取る情報に違いがあるのではないか、と仮設を立て、検証を進めているところです。
これまで、教師の認知や思考は、主にインタビューによる聞き取りで調査してきました。しかし、人間は経験に基づいて直感的に行動することが多く、「あなたは授業中どこをよく見ていますか?」と聞いても、はっきり答えられない教師が少なくありません。従来のインタビューに加えて、授業をリアルに再現でき、かつVR映像の視聴行動を録画することで、教師がどこに注目しているかを捉えやすくなるメリットもあると考えています。
教師の思考過程を分析しICT活用のヒントを探る
国のGIGAスクール構想により、全国の学校にタブレット端末が導入され、ICT環境の整備も進んでいます。しかし、機械さえそろえば教育が良くなるわけではありません。教師も子どもも、ICTの「良き使い手」になる必要があり、教育実践を通して支える教師の授業力量(わざ)はやはり重要だと言えます。さらに、授業でICTを効果的に活用するためには、機械の操作に詳しいだけでは不十分で、「教科内容、指導法、テクノロジー」の3つの知識を融合させて創造的に授業をデザインする力が求められます。
そこで、教師がICTを活用した授業計画や指導案をつくる際の思考過程を分析し、3つの知識をどのように結び付けて授業を組み立てているのか、そのプロセスにおいて教師のハードルになるものは何かを検討したいと考え、研究をスタートさせました。
授業のデジタル化に関しては、教師によってさまざまな向き合い方、考え方がありますが、デジタル化に積極的な教師が「良い先生」、消極的な教師が「遅れている」と一概に言うことはできません。「以前の教え方で身に付いていた力が、デジタルでは身に付かないから」など、明確な意図を持ってタブレットを使っていない教師は、無批判にタブレットを使っている教師よりも、ある意味で、ずっとICT活用の意味を思考しているとも言えます。こうした多様な教師間の議論を通じて、効果的なICT活用授業を支えるヒントをつかみ、個々の教師の個性を生かしながらより良いICTの活用に繋げることができればと考えています。
今後の展望
成長を実感できる幸せな教師を増やしたい
研究を通して私が目指しているのは、教師による授業の奥深さ、素晴らしさを解き明かすことです。近年教育現場では、1970~80年代に大量採用された教師が退職の時期を迎え、教師の平均年齢が低下しています。それ自体は決して悪いことではありませんが、退職によってベテラン教師が持つ授業力量(わざ)が失われてしまわないよう、後進に伝承していく必要があると思います。優れた授業の奥に隠された素晴らしい知を解明し、多くの教師に共有可能なカタチにしていくことは、研究者としての私の使命だと考えています。
一方で、「分かること」と「できること」は違います。我々研究者が理論を伝えるだけで教育実践が変わるほど、教育は簡単なものではありません。論文を読めば誰でも優れた教師になれるわけではない以上、研究者も現実の教育実践に無責任ではいられません。教育研究者として、教育現場とのパートナーシップを進めながら、協働で問題解決を試み、教師が成長していくシステムを構築していきたいと思っています。

これまでたくさんの教師にお話を聞いてきましたが、優れたわざを持つ教師に共通しているのは、みなさん毎日楽しそうに授業をしているということです。授業の中で気付きがあり、それをヒントに教師自身も成長する。そうした日々の変化は、きっと教師としてのやりがいや喜びを生むものなのでしょう。研究を通して教師の成長を支援し、一人でも多くの教師が変化を実感して幸せになれるよう、力を尽くしていきたいですね。
教育
多面的視点で授業をデザインする力を育てる

教育学部では「教育の方法と技術」「ICT活用論」の授業とゼミの指導を担当しています。武蔵野大学の学生は、本当に真面目で勉強熱心ですね。私の研究は教師の成長をサポートする研究ですが、武蔵野大で教師を目指す学生はすでに学び続ける姿勢をしっかり持っていて、その姿に刺激を受けています。
「教育の方法と技術」の授業では、発問や指示など授業の技術に関する内容だけでなく、学習環境など潜在的に教育に影響を与える要素にも触れ、さまざまな観点から「より良い授業」について考えていきます。良い授業とは、決して教師が上手に話すだけでつくられるものではありません。たとえばディスカッションをする時の机の配置、教室の整理整頓といった周囲の環境も、子どもの学びを大きく左右する1つの要素となります。そうした要素にも目を向ける大切さを伝え、多面的、総合的に授業づくりを考える面白さを感じてほしいと思っています。
多面的に考えるという点では、ICT活用に関する授業を担当してはいますが、「ICTを使えば良い授業ができる」と無批判的になってほしくないとも思っています。たとえば、スクリーン等でスライドを提示すると、教師の板書時間を減らし、情報も見やすくなるというメリットがありますが、画面が次々に変わってしまうため、授業がどう進んできたのかが捉えにくくなります。その意味で、一目で授業の流れが分かる従来の黒板にもメリットがあるといえます。アナログとICTの特徴を理解し、場面に合った教え方を選び、ときには組み合わせたりしながら効果的な授業をデザインする力をつけられるよう指導しています。
一人一人個性を持つ子どもたちを相手にしている以上、教師の「教え方」に唯一の正しい答えはないように思います。学生には、目の前の子どもを見て、その子どもに合った答えを子どもと一緒につくっていくことができる教師になってほしいと願っています。
人となり
中学で始めたバスケが趣味

趣味はバスケットボール。するのも観るのも好きです。中学でバスケ部に入り、高校までは練習漬けの毎日でしたし、大学はプロ選手が出るくらい“ガチめ”のサークルで頑張っていました。大学院に入り、研究が忙しくなってからは少し遠ざかっていたのですが、最近よく一人で練習するようになりました。何も考えずに、ひたすらシュートを打ち続けているだけで楽しいです。観る方はNBAの中継をよく観ていて、今はボストン・セルティックスを応援しています。アメリカに行って生で試合を観るのが夢なので、チャンスをうかがっているのですが、なかなか実現できないですね。
おいしいものを食べて作ってリフレッシュ
休日は、行列のできる有名店を回っておいしいものを食べてリフレッシュしています。おいしいものを食べると自分でも作りたくなってしまって、家ではいろいろなレシピにチャレンジしています。料理ができるのは、学生時代お金がなくてもっぱら自炊だったから。当時は八百屋さんや肉屋さんで「これどんな料理にしたらおいしいですか?」「いつもおひたしなんですけど、ほかにおいしい食べ方ありますか?」みたいなことを聞いてレパートリーを増やしていました。買い物に行って面白そうな調味料を見つけるとつい買ってしまうので、キッチンは調味料やスパイスだらけ。スパイスを自分で組み合わせて、カレーを一から作ったりもしています。

▲先生お気に入りのスパイス集

▲先生お手製のラムキーマカレー
読者へのメッセージ

インターネットやSNSの普及により、さまざまな場で多様な人から学ぶことができる時代になりました。ただ、時代が変わっても、人生における教師の影響力は今なお大きいのではないでしょうか。最近は「過酷」「ブラック」といったネガティブな側面にばかりが取り上げられますが、私のゼミの卒業生は本当に楽しそうに、充実した教員生活を送っています。学校の教師は、とても創造的で素晴らしい仕事です。これからさらに研究を深め、教師が持つ力や授業の奥深さを知る機会をつくり、教師の成長を少しでも支えていきたいと思っています。
取材日:2025年2月

